国際平和協力隊員の声
国際平和協力法により世界各地に派遣された(派遣されている)隊員からメッセージが届いています。
(※各写真をクリックすると、それぞれのメッセージがご覧いただけます。)




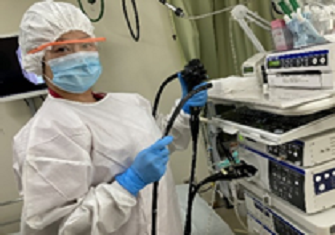







(※各写真をクリックすると、それぞれのメッセージがご覧いただけます。)
【一口メモ】
東ティモール選挙監視国際平和協力隊(2007年)についてはこちら。
ネパール選挙監視国際平和協力隊についてはこちら。
| 私は、2007年東ティモール大統領選挙決選投票、議会選挙、2008年ネパール制憲議会選挙に選挙監視団の一員として派遣されました。選挙監視とは、自由かつ公正に選挙が行われたかという視点で、選挙準備、投開票や集計プロセスを見守る活動です。特に東ティモールやネパールでは、政情が不安定で直前まで暴力が多発していました。そのため、安全が確保され、人びとの意思が投票を通じて代表者の選出に反映されるかが重要な課題でした。 当時は国際平和協力研究員として、内閣府国際平和協力本部事務局に勤めており、監視活動の準備と活動後のフォローにも参加しました。準備で重要なのは、各国の憲法、選挙法等に基づき、確認すべきポイントを列挙し、チェックシートを作成することでした。このシートを用いて、中立性を保ちつつ、善意の傍観者としての態度をもって監視活動にのぞみました。活動後は各団員の報告をもとに評価・提言としてまとめ、各国政府に伝えています。例えば、投票所における警察官の立ち位置、二重投票防止インクを付す場所の再確認といった手続きの厳格化の徹底、開票時の有効・無効の判断についてマニュアルの作成といった提言です。 赤ちゃんを抱きかかえた女性や老人の方々も含め、人びとが朝早くから投票のために投票所前に並ぶといった、日本ではみられないような状況を目の当たりにし、平和への試金石となる選挙への関心の高さが窺(うかが)えました。監視団長は、「選挙により反映された民意を、敗者を含めすべての国民が受け入れることが重要」と述べていました。引き続き、世界各国において人びとが平穏な暮らしを取り戻すためにも、非暴力による政治的競争が進められることを願っています。 |
|


【一口メモ】
ネパール国際平和協力隊、UNMIN(国連ネパール政治ミッション)についてはこちら。
スーダン国際平和協力隊、UNMIS(国連スーダン・ミッション)についてはこちら。
|
|
私は、平成20年3月~平成21年3月の1年間、ネパールにおける国連の特別政治ミッション(SPM)であるUNMINに軍事監視要員として派遣され、首都カトマンズのネパール国軍武器保管施設、地方に点在するマオイスト軍(反政府ゲリラ)の駐屯施設で勤務しました。この間、制憲議会選挙において投票するマオイスト軍の監視等の様々な軍事監視業務を通じて、新しい国づくりの一端を垣間見ることができました。 また、平成23年には、南スーダン独立前のスーダンにおける国連の平和維持活動(PKO)であるUNMISに司令部幕僚として派遣され、UNMISが任務終了し南スーダンのUNMISSに移行するまでの3ヶ月間、首都ハルツームで勤務しました。この間、情報幕僚業務を通じて、スーダンによるアビエイ地区侵攻など、一国の自治地域が別の国として分離独立するまでの困難を体感することができました。 こうした海外での勤務は、不思議と自分や日本のことを客観的に眺める機会にもつながり、日本人の所作や考え方、自衛隊勤務において身に付ける自衛官としての仕事の作法や軍事合理的な思考方法などが、世界で通用することを体感しました。 これらの貴重な経験を通じて私なりに体得させていただいた国際平和協力活動マインドは、国際平和協力活動に従事する隊員を育成する国際活動教育隊における現在の私の勤務に活かされています。 |


【一口メモ】
ハイチ派遣国際救援隊(自衛隊の部隊)、MINUSTAH(国連ハイチ安定化ミッション)についてはこちら。
| 私は、第4次ハイチ国際救援隊のカウンセラーとして派遣されました。2011年2月に現地入りし、間もなく東日本大震災が発災しました。派遣隊員たちはBS放送で繰り返し映される津波の光景を見て、大変不安定な心理状態に陥りました。カウンセラーとして、隊員の心理状態を把握するために活動現場の巡回を毎日欠かさず行い、隊員のケアに必死だったと記憶しています。 また、当時私の娘は小学校6年生であり、派遣中は実家から母が来て面倒を見てくれていました。ハイチ派遣時には、娘は小学校卒業・中学校入学という節目の時期でした。過去に2005年の第6次イラク復興支援群に派遣された際も、小学校に入学したばかりという不安の大きな時期の娘を母に預けて参加しました。私自身も娘の成長過程での重要な時期と派遣が重なることについては、複雑な心境でしたが、幹部自衛官としての任務を優先するべきでありやむを得ないと考えていました。 2回の長期に渡る海外派遣に参加する私の姿を娘がどんな想いで見ていたのかを知ったのは、実は最近のことでした。ふとしたきっかけで娘が本音を語ったのです。「ママは仕事が一番大事なんだと思ってた」と。家族とはお互い寂しい想いを共有していて派遣についても理解してくれていたと思い込んでいた私は、衝撃を受けました。私には任務に対する強い使命感があったこと、母親として複雑な想いであったこと、そして、そんな私を育ててくれた母が誰より身近で支援をしてくれたからこそ、安心して厳しい任務をやり遂げられたことを伝えることができました。娘は「寂しい想いもしたけれど、自衛隊の看護官であるママを誇りに思っている」と言ってくれました。 カウンセラーとしてはクライエントに寄り添う姿勢が基本である中、娘には厳しい姿勢が基本になっていたことに気づかされました。派遣から10年経ち改めて、任務達成できたのは、娘の笑顔と母の支援のおかげであると感謝してます。 女性自衛官の活躍がよりいっそう期待される中、私や家族がPKOを通じて経験したことを踏まえ、後輩隊員に柔軟なサポートや指導ができ、有意義な活躍ができる環境を醸成していきたいと考えます。 |
|
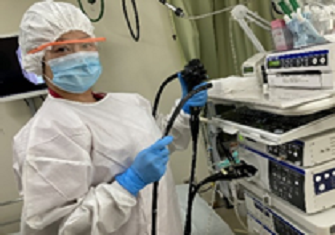

【一口メモ】
ゴラン高原派遣輸送隊(自衛隊の部隊)、UNDOF(国連兵力引き離し監視隊)についてはこちら。
なお、日本からUNDOFへの派遣は約17年(1996年~2013年)と過去最長で、その撤収が決まった時の話です。
|
|
その瞬間の隊員たちの目が忘れられない。 2012(平成24)年12月、日本政府は折からのシリア国内情勢の悪化を受け、「我が国の要員の安全を確保しつつ、意義のある活動を行うことが困難」との見解に基づき、国連兵力引き離し監視隊(UNDOF)からの日本隊の撤収を決定した。私は隊長として、43名の部下たちに、現地での国連部隊としての活動停止、日本への帰国準備を命じなければならなかった。 会議室に隊員を集め、これを告げると、隊員たちは束の間瞬きを忘れたように大きく目を見開き、押し黙った。長い沈黙-あるいはそれほど長くもなかったかもしれないが-の後、一人の隊員が口を開いた。 「あの、それじゃあ、いつ戻って来られるのでしょうか?」 私は衝撃を受けた。昨夜もUNDOFの作戦地域ではシリア政府軍と反政府軍の衝突があり、宿営地にも砲声が響いていた。緊張を強いられる状況である。しかしその隊員は、我々が任務を中断することによる他への影響をまず気にかけ、いずれ戻って任務に復帰する心づもりであったのである。 私は己の不明を恥じた。共にこの地で汗を流す仲間たちは、私が思う以上に誇り高きピースキーパーだったのである。 1996年以来の我が国のゴラン高原での活動は、UNDOF司令部、各国部隊からの日本隊への信頼を揺るぎないものとしていた。それは長い年月をかけ積み重ねられた重厚な氷床の様でもある。そして寄せられる信頼は、いつしか我々の誇りとなっていた。 そうであればこそ、17年間の派遣任務に携わったすべての人々の積み重なる想いが、隊員にあの言葉を言わしめたとも感じるのである。国際任務への使命感もまた、一朝では醸すことはできない。 |


【一口メモ】
シナイ半島国際平和協力隊、MFO(多国籍部隊・監視団)についてはこちら。
| 私は、シナイ半島国際平和協力隊の3次要員として派遣され、現在、エジプトのシナイ半島で活動する多国籍部隊・監視団(MFO)の南部地域担当の連絡調整部副部長として勤務しています。 MFOの要員は、日本の他、アメリカやヨーロッパを中心に合計13か国から派遣され、エジプト・イスラエル両国のシナイ半島における信頼構築等のため活動しています。 連絡調整部は、(1)MFO部隊の恒常的業務の支援及び行動の容易化、(2)エジプト及びイスラエル関係機関との調整業務、(3)MFOへの協力国との関係強化等を通じ、MFOの活動全般を支える業務を行っています。 私は、南部地域担当の副部長として、各国の要員(アメリカ、イタリア、ノルウェー)及び現地雇用職員を指揮しつつ、主に、エジプト政府関係諸機関との連絡調整業務を行っています。特に、南部地域には、MFOの活動に欠かせない司令部、基地、通信施設、国際空港、港湾等が所在しており、施設への入場や輸送の手続、各国部隊等の交代における手続(通関手続や在留証明書の発行手続等)、高官等のMFO訪問支援といった多岐にわたる業務を担当しております。 ここでの勤務を通じ、当初は、エジプトの文化や多国籍部隊ならではの苦労もありましたが、相手を尊重し、お互いに理解することで、チームとして共通の目標に向かって任務を遂行できること、また、これまでの勤務で培った経験に基づき、状況に応じてバランスをとりながら業務を行うことで、十分に多国籍部隊において役割を果たせるということを実感しています。 派遣にあたり、日本の関係者をはじめ、多くの方々のご支援・ご協力により、職場環境及び居住環境も充実し、大変やりがいのある日々を過ごしています。 今後も、MFOやエジプト・イスラエルの関係者との信頼関係を維持しつつ、エジプト・イスラエル両国の永続的平和のため、日本の要員としての役割を果たしていきたいと思います。 |
|


【一口メモ】
南スーダン国際平和協力隊、UNMISS(国連南スーダン共和国ミッション)についてはこちら。
|
|
私は令和3年8月からUNMISSミッション支援部施設課の施設幕僚として勤務しています。南スーダンへの派遣は2度目で、1度目は派遣施設隊の広報を担当していました。この経験が今でも役に立っているので紹介します。私は地域住民へのインタビューを通じて、日本隊が作った道路の排水溝が、家の中に流れ込んできた雨水の流入を防いで衛生環境を改善し、更には地域の交通の便を良くしたという生の声を直接聞いていました。 現在、日本隊が撤収した後でも、勤勉で丁寧な当時の日本隊の仕事ぶりを評価し、懐かしみ、私に親しく話しかけてくれる関係者は思いのほか多く、その日の丸への信頼貯金のお陰で、私が今現在円滑に仕事をさせていただいていると感じています。 現在、私は南スーダン全土に及ぶ、主要幹線道路の整備に携わっています。工事を行うインド、中国、韓国、パキスタン、タイ、バングラデシュの部隊のほか、南スーダン政府や各州関係者、NGOといった多様な関係者と調整し、その努力を統合していく非常にダイナミックな仕事です。 私は、この仕事を「単なる道路整備」とは思っていません。1度目の派遣で学んだように、道路は人、モノ、食料、医療へのアクセスを可能にするとともに、治安の改善や人的交流を促進する平和構築プロセスそのものと認識しているからです。自分の目の前の仕事が「誰のどんな問題を解決するか」を具体的に考えていくことで付加価値を生み、地図と人々の心に残る仕事に繋がると信じています。 諸先輩方が残してくれた日の丸への信頼貯金、私もコツコツと積み立てていきたいです。 |









