若年層を中心とした消費者教育の効果的な推進に関する提言
2016年6月28日
消費者委員会
目次
- はじめに
- 第1 若年層の消費者を対象とした消費者教育の現状
- 第2 若年層を対象とした消費者教育の取組事例
- 第3 若年層の消費者教育に関する調査
- 第4 コーディネーターの活用による学校における消費者教育の充実
- 第5 提言
- 【今後の展望】子供・若年層に焦点を合わせた消費者教育
- 【今後の展望】消費者教育に市民権を
- 参考資料1
- 参考資料2
はじめに
(消費者基本法)
消費者基本法(昭和43 年法律第78 号)では、消費者に対し必要な情報及び教育の機会が提供されることは消費者の権利であると位置づけ、消費者政策は、消費者が自らの利益の擁護及び増進のため自主的かつ合理的に行動することができるよう消費者の自立を支援することを基本として行わなければならないとされている(第2条第1項)。
同法では、消費者は自ら進んで消費生活に関して必要な知識を習得し、必要な情報を収集する等自主的かつ合理的な行動に努めなければならないとされており(第7条第1項)、国は、消費者の自立を支援するため、消費生活に関する教育を充実する等必要な施策を講ずるものとされている(第17 条第1項)。
(消費者教育の推進に関する法律及び消費者教育の推進に関する基本方針)
また、消費者教育の推進に関する法律(平成24 年法律第61 号。以下「消費者教育推進法」という。)においては、基本理念の一つとして、消費者教育は、消費生活に関する知識を修得し、これを適切な行動に結び付けることができる実践的な能力が育まれることを旨として行われなければならないことを掲げている。
さらに、同法第9条では、政府が消費者教育の推進に関する基本的な方針を策定するに当たっては、当委員会にも意見を聴くこととされていることから、当委員会は「消費者教育の推進に関する基本方針の策定に向けた意見」(平成24 年12 月25 日)を述べている。
政府は、当委員会の上記意見等を受けて、消費者教育の推進に関する基本方針(平成25 年6月28 日閣議決定。以下「基本方針」という。)を策定している。
国及び地方公共団体は、これらの法律及び基本方針に基づいて、消費者教育の諸施策を推進しているところである。
(若年層(注1)の消費者に対する消費者教育の重要性)
消費者教育は、幼児期から高齢期までの各段階において行われているが、教育委員会における消費者教育の実施や、消費者行政部局との連携は十分とは言えないとの指摘があるなど、消費者教育の充実・強化のためには、なお一層の工夫と努力が必要と考えられる。
特に、若年層では消費者問題に係る知識や社会経験の乏しさから、知らず知らずのうちに消費者問題に係る犯罪の加害者に加担することもあり、また、選挙権年齢の引き下げに合わせて成年年齢が18 歳に引き下げられた場合には、高校生であっても契約の責任を自ら負うことが考えられることなどから、若年層の消費者に対する消費者教育がより重要になる。
- (注1) 本提言において、「若年層」とは、小学生から20 代前半までの年齢層とする。
こうした問題意識のもと、当委員会は、若年層を中心とした消費者教育の効果的な推進の方策を探るべく調査を実施した。
以下、第1では、若年層の消費者を対象とした消費者教育の現状について国、地方公共団体等におけるそれぞれの取組について述べた。
第2 1では、若年層の消費者問題の状況について把握するため、年齢別の相談件数や具体的な相談事例について記載した。また、第2 2では、教育委員会や学校(注2)等へのヒアリングをもとに、学校において、どのような消費者教育が実施されているのか具体的な取組事例を紹介した。
第3では、学生3に消費者教育に関するヒアリングを実施し、その結果から消費者教育を実施していく上で重要と考察されることをまとめた。
第4では、地域において、教育委員会と消費生活センターとの連携の促進や、学校の教員等と連携した教材開発を行う等、消費者教育の推進に効果的な活動を行っているとみられる「消費者教育コーディネーター」の活動事例を記載した。
第5では、第1から第4までを踏まえ、消費者教育の裾野を広げ、消費者教育が一層推進されるために、今後、関係行政機関がとるべき方策について当委員会としての提言を述べた。
- (注2) 本提言において、「学校」とは、他に規定するものを除き、学校教育法(昭和22 年法律第26 号)第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)、第124 条に規定する専修学校及び第134 条に規定する各種学校とする。
- (注3) 本提言において、「学生」とは、他に規定するものを除き、学校教育法の学生とする(具体的には、大学及び大学院の学生をいう(消費者委員会事務局注)。)。
第1 若年層の消費者を対象とした消費者教育の現状
消費者教育については、平成24 年12 月に施行された消費者教育推進法や、同法に基づき策定された基本方針を基に、国及び地方公共団体において各種施策が実施されている。
特に、若年層を対象とした消費者教育について、消費者教育推進法では、国及び地方公共団体は、児童・生徒に関しては、その発達段階に応じて、学校の授業その他の教育活動において適切かつ体系的な消費者教育の機会を確保するため、必要な施策を推進しなければならない(第11 条第1項)とし、大学生等に関しては、大学等において消費者教育が適切に行われるようにするため、大学等に対し、学生等の消費生活における被害を防止するための啓発その他の自主的な取組を行うよう促すものとする(第12 条第1項)とされている。
これを受け、基本方針では、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校等においては、学習指導要領の趣旨の周知・徹底を図り、各教科において充実した消費者教育が行われるよう努めるとともに、教材の開発、教職員の指導力向上、外部人材の活用、関係機関との連携の促進などの取組を推進することとされている。
また、大学・専門学校等においては、国は、大学等が学生一人一人の状況に留意しつつ、消費者教育を展開することができるよう、先進的な取組事例の情報の収集・提供を行うとともに、学生支援に従事する大学等の教職員を対象とした会議の場等における消費者問題の情報提供及び注意喚起を行うこととされている。
【参考:消費者教育の体制(イメージ)】
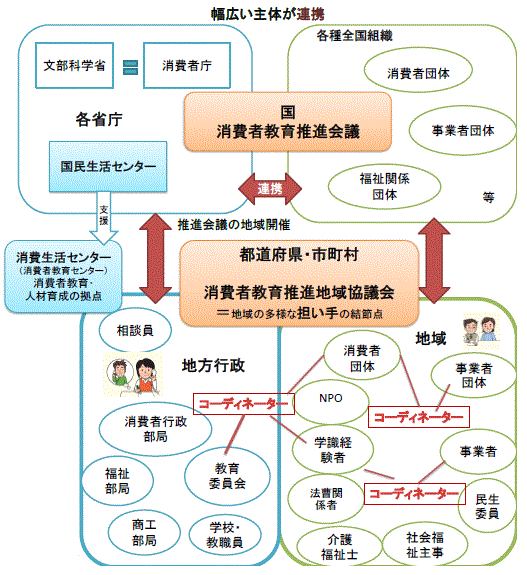
出展:消費者庁作成資料
1 国における取組
(1)消費者庁
ア 消費者教育推進会議
消費者庁には、消費者教育推進法第19 条に基づき、消費者教育推進会議(以下「推進会議」という。)が設置されている。推進会議は、消費者、事業者及び教育関係者、消費者団体、事業者団体その他の関係団体を代表する者、学識経験者並びに関係行政機関及び関係する独立行政法人の職員のうちから、内閣総理大臣が任命した委員により構成されており、消費者教育の体系的かつ効果的な推進に関して委員相互の情報交換及び調整を行っている。
若年層を対象とした消費者教育については、推進会議において、学校での消費者教育の一層の充実を図るための方策の検討を行った。平成28 年4月には、推進会議での検討結果を基に、「学校における消費者教育の充実に向けて」(注4)を公表し、マル1消費者教育の機会の確保、マル2教員の消費者教育指導力向上のための教育・研修、マル3外部人材の活用について提案している。
- (注4)消費者庁の報告書・資料等(http://www.caa.go.jp/policies/council/cepc/other/)「学校における消費者教育の充実に向けて(平成28年4月28日)」
イ 消費者教育ポータルサイト
消費者庁では、消費者教育に関する様々な情報を提供するために、消費者教育ポータルサイト(http://www.caa.go.jp/kportal/index.php)を開設している。
消費者庁は、このポータルサイトを通じて、自ら作成した消費者教育に関する教材だけでなく、他の関係行政機関や関係団体等が作成した教材も提供しているほか、地方公共団体、公益法人、NPO、各種関係団体等が行っている取組等に関する消費者教育に関する各種情報の収集・提供を行っている。
ウ 国と地方のコラボレーションによる先駆的プログラム
消費者庁は、地方消費者行政推進交付金により、消費者の安全・安心の確保に向け、消費者問題に関する先駆的なテーマを国から提案、問題意識を共有した上で、地方公共団体の自主性・独自性を確保しつつ、地方の現場での実証実験等を行う、「国と地方のコラボレーションによる先駆的プログラム」を実施している。このプログラムにより実施された事業の成果・課題等については、事業終了後に報告書を作成・公表し、全国的な波及・展開を目指すこととしている。
平成27 年度には、消費者教育の推進に関するテーマとして、「地域における多様な担い手の連携・協働、風評被害の防止等」を国から提案しており、このテーマに沿うものとして10 県9市において33 事業が実施された。
このうち、若年層に対する消費者教育に関するものには、「親子で学ぶ消費・金融教室」(福島県)や「子供のための消費者教育講座(中学校対象)」(岐阜市)、「特別支援学校における消費者教育の推進」(兵庫県)、「消費者教育コーディネート人材養成事業」(岡山県)、「高校・大学生指導者用教材作成事業」(熊本市)などがある。
エ 消費者教育の体系イメージマップ
消費者庁では、平成24 年9月に「消費者教育推進のための体系的プログラム研究会」を設置し、25 年1月に幼児期から高齢期までの各段階における消費者教育の重点領域をマトリックス状の一覧表で示した「消費者教育の体系イメージマップ」を作成・公表している。
また、併せて、「消費者教育の体系イメージマップ」活用ガイドを作成し、イメージマップの活用方法や展開モデル例を示している。
なお、このイメージマップ及び活用ガイドは、上記の消費者教育ポータルサイトに掲載されている。
(2)文部科学省
ア 連携・協働による消費者教育推進事業
文部科学省では、平成25 年度から、地域における消費者教育が一層推進されるよう、教育行政を含む連携・協働体制づくりを支援するため、消費者教育推進委員会の設置や消費者教育アドバイザーの派遣等を内容とする「連携・協働による消費者教育推進事業」を行っている。
(ア)消費者教育推進委員会
消費者教育推進委員会は、消費者教育に関する有識者等により構成され、文部科学省における消費者教育の推進方策等について検討を行っている。平成27 年度には本委員会において、教員や社会教育主事を対象に、消費者教育を行う上でのヒントを示し、学校や社会教育における消費者教育の充実を図るため、「消費者教育の指導者用啓発資料」を作成。平成28 年度にはその活用を図っている。
(イ)消費者教育アドバイザー
文部科学省では、地域における消費者教育が、連携・協働により一層推進されるよう、有識者や実践活動者を消費者教育アドバイザーとして、地方公共団体等からの求めに応じて派遣している。
消費者教育アドバイザーは、地方公共団体等の求めに応じて、様々な活動を行うが、例えば、マル1地方公共団体における消費者教育推進方策に係る指導助言、マル2消費者教育に関するフォーラム等における講演、パネリスト、マル3教職員、民生委員、社会教育主事等に対する研修等の講師、マル4地域における連携・協働体制構築のためのコーディネーター等が挙げられる。
(ウ)消費者教育連携・協働推進全国協議会
文部科学省の消費者教育に関する事業の成果を広く還元するとともに、消費者教育を実践する多様な主体と連携・協働することにより消費者教育の更なる推進を図るという趣旨で、全国各地で消費者教育フェスタや消費者教育実践フォーラム(消費者庁と共催)として開催している。
(エ)連携・協働による消費者教育推進のための実証的調査研究
文部科学省は、自主的な消費者教育の推進体制づくりが困難な地域を想定し、効果的な教育体制を実証することを目的とした調査研究を実施することとしている。この調査研究は、地域の教育委員会や関係機関等で実行委員会を組織した上で、社会教育の仕組みや取組を活用し、連携・協働により消費者教育を実施するものである。
(オ)消費者教育に関する現況調査
文部科学省では、平成22 年度及び25 年度に、「消費者教育に関する取組状況調査」を行い、全国の教育委員会及び大学等に対して、消費者行政部局等との連携状況や学校教育関連の取組等について調査している。
平成25 年度の調査によれば、消費者行政部局等との連携のために連絡協議会を設置している都道府県・政令市教育委員会は、22 年度37.9%から25 年度50.7%に、市区町村教育員会は、同0.9%から同5.6%にそれぞれ増加している。また、平成25 年度に教職員を対象とした消費者教育に関する内容を含む研修を実施(他機関が主催する研修への派遣を含む。)している教育委員会は全体の15.3%であり、このうち消費者教育に特化した研修を実施しているのは25.4%となっている。
なお、平成28 年度に同様の調査を実施する予定である。
イ 学習指導要領における消費者教育
学習指導要領には、従来から消費者教育に関する内容が盛り込まれていたが、平成20 年及び21 年の改訂の際に、下表のとおり社会科、公民科、家庭科、技術・家庭科等の教科を中心に消費者教育の充実が図られている。
現在、学習指導要領の改訂作業が行われており、次期学習指導要領(注5)には、消費者教育に関係するものとして、高等学校の公民科における共通必履修科目として、主体的な社会参画に必要な力を、人間としての在り方・生き方の考察と関わらせながら実践的に育む科目「公共(仮称)」の設置などが検討されている。
表 現行の学習指導要領における消費者関係教育に関する主な内容
| 教科 | 主な内容 | |
|---|---|---|
| 小学校 | 社会科 | ・ 地域の社会生活を営む上で大切な法やきまりについて扱う |
| 家庭科 |
|
|
| 特別の教科道徳 |
※ 平成27 年3 月に一部改訂。平成30 年度から全面実施。 |
|
| 中学校 | 社会科(公民) |
|
| 技術・家庭科 |
|
|
| 特別の教科道徳 |
※ 平成27 年3 月に一部改訂。平成31 年度から全面実施。 |
|
| 高等学校 | 公民科 |
|
| 家庭科 |
|
(注) 本表は、消費者委員会事務局において作成した。
- (注5) 前回改訂時のスケジュールを踏まえた場合、小学校は平成32 年度から、中学校は平成33 年度からそれぞれ全面実施予定。高等学校は、平成34 年度から順次実施予定。
ウ 大学等及び社会教育における消費者教育の指針
消費者教育推進委員会では、大学等及び社会教育における消費者教育の目的と戦略を明確にし、消費者教育の推進とその内容の充実に関する大学等及び社会教育の役割、効果的と考えられる教育のあり方等について「大学等及び社会教育における消費者教育の指針」(平成23 年3月30 日)を取りまとめている。
この指針では、大学等に対し、学生に対する各種の消費生活や消費者問題に関する情報や知識の提供機会の拡大や、自立した社会人としての消費者、また、職業人としての生産者・サービス提供者の育成が求められるとしている。このため、大学等における消費者教育の内容・方法として、啓発・相談、教育・研究、地域貢献、サークル・自主活動に分けて具体的に示している。
(3)その他関係府省庁
消費者教育推進法第3条第7項では、消費者教育に関する施策を講じるに当たっては、消費生活に関連する教育に関する施策との有機的な連携を図ることが求められている。
消費生活に関連する教育としては、例えば、環境教育や食育、国際理解教育、法教育、金融経済教育などがあり、それぞれ関係府省庁において取組が進められている。
2 地方公共団体における取組
(1)消費者教育推進地域協議会
都道府県及び市町村は、消費者教育推進法第20 条に基づき、消費者教育推進地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置するよう努めることとされている。地域協議会は、消費者、消費者団体、事業者、事業者団体、教育関係者、消費生活センター等により構成され、当該都道府県又は市町村の区域における消費者教育の体系的かつ効果的な推進に関して委員相互の情報交換及び調整を行うこととされている。
平成28 年3月23 日現在、42 都道府県で地域協議会が設置されている。
(2)都道府県消費者教育推進計画等の策定
都道府県及び市町村は、消費者教育推進法第10 条第1項及び第2項に基づき、基本方針を踏まえ、都道府県消費者教育推進計画又は市町村消費者教育推進計画を策定するよう努めなければならないとされている。
平成28 年3月23 日現在、30 都道府県で都道府県消費者教育推進計画が策定されており、それぞれの地域の特性に応じて、関係団体との連携方策や、幼児期から高齢者までの各段階に応じた取組などを定めている。
(3)コーディネーターの育成
基本方針では、消費者教育を担う多様な関係者の間に立って調整をする役割を担う者(コーディネーター(注6))は、消費者市民社会形成の推進役としての重要な役割を果たすとしており、消費生活センター等が拠点となり、消費者教育を担う多様な関係者が連携・協働した体制づくりが進むよう、コーディネーターの育成に取り組むこととされている。
平成27 年4月1日現在、このようなコーディネーターは、全国の11 都道府県78 市区町村等で設置されている(注7)。
3 関係団体等における取組
若年層を対象とした消費者教育は、国や地方公共団体だけでなく、消費者団体や事業者、事業者団体等の関係団体等も実施主体となり、学校を始めとした様々な場で行われている。
関係団体等における取組(注8)としては、例えば、消費者団体による学校等の消費者教育に関する要望に沿って自ら作成したタイムリーな教材を用いて行う出前授業や、対象者の年齢に合わせた教育プログラムの開発などがある。また、事業者・事業者団体が、自らが提供している商品・サービスに関して、消費者トラブルに遭わないために必要な知識等の普及啓発に取り組んでいる例もある。
- (注6) このような役割を担う者の名称は、設置している地方公共団体により様々であり、例えば、岡山県では「消費者教育コーディネーター」と、千葉県柏市では「消費者教育相談員」と称している。本提言では便宜上、このような者を「コーディネーター」と呼ぶこととする。
- (注7) 「平成 27 年度 地方消費者行政の現況調査」(平成27 年11 月消費者庁)参照。
- (注8) 関係団体等の取組は、消費者庁が開設している消費者教育ポータルサイト(http://www.caa.go.jp/kportal/index.php)に掲載されている。
第2 若年層を対象とした消費者教育の取組事例
1 若年層の消費者における消費者問題の状況
15 歳から29 歳までの年齢別の相談状況について、PIO-NET(注9)に登録された相談データによると、図のようになっている。
図 若年層の相談件数(注10)(平成27 年度)
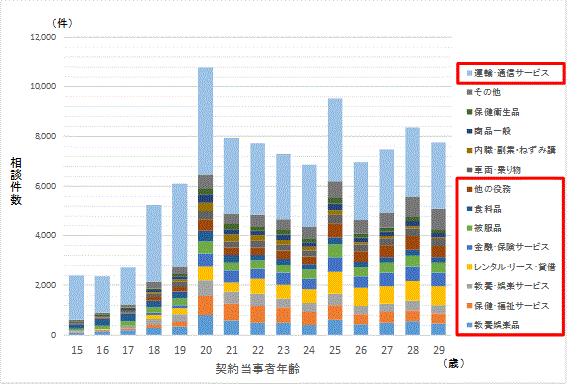
いずれの年齢においても、運輸・通信サービスに係る相談が多くなっていることがわかる。また、18 歳や20 歳といった就職や大学入学等による環境変化、成年年齢に達する時に相談件数が増加する傾向が認められる(注11)。
内訳をみると、19 歳から20 歳にかけて、ほぼ全ての項目で相談件数が増加している。中でも、金融・保険サービス(ローン関係等)や保健・福祉サービス(エステの契約関係等)の増加率が高い。
- (注9) PIO-NET(パイオネット:全国消費生活情報ネットワークシステム)とは、独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)と全国の消費生活センター等をオンラインネットワークで結び、消費生活に関する相談情報を蓄積しているデータベース。
- (注10) PIO-NET に登録された消費生活相談情報(平成27 年度に受け付け、平成28 年4 月30 日までに登録された相談件数)
- (注11) 契約当事者年齢について、相談受付の際に「20 代半ば」等と詳細な年齢の説明が無かった場合、20 歳または25 歳と登録される場合がある。
このような背景には、20 歳で成年となり、契約等を行うことが可能になることが影響しているともみられる。さらに、高校から大学へ進学したり就職すること等により、生活環境が変わることが多い場合があることも関係しているとみられる。
今後、仮に成年年齢が引き下げられ、未成年者契約取消の対象となる年齢が低下すると、これらの消費者相談や消費者問題がより低年齢の層においても増加する可能性がある。
それぞれの分類項目における具体的な相談内容は以下のとおりである。
(1)運輸・通信サービス
相談事例1 スマホにメールが届き、サイトに登録し、男性の相談にのるだけで報酬がもらえると言われた。
スマホにメールが届き、安全なメール副業というサイトで携帯電話さえあれば誰でも参加OKと記載があり空メールを送信した。そのサイトからメールが届くようになり、サイトのある男性から相談に乗ってくれたら毎月高額な謝礼を渡すと言われた。その男性の相談に乗っていたら、サイトからメールが届き、男性と個人情報を交換するためにポイントを購入するよう言われた。男性は、初めからポイント購入は分かっていたはずだと言った。私はポイント購入をしなければならないことを知らなかったが、その男性は個人情報を交換できるようにしたらポイント購入に支払った金額は戻ってくると言った。私はその男性の言葉を信じ数回ポイント購入のためにクレジットカード決済をして2つの決済代行業者に約30 万円を支払った。免許証や銀行の口座番号をサイトに伝えた。しかし何度ポイント購入しても個人情報の交換はできなかった。騙されたとわかったので返金してもらいたい。
(20 歳:女性)
(2)教養娯楽品
相談事例2 大学の友人に誘われて借金して投資用教材USBを購入したがクーリング・オフしたい。
同じ大学のクラスメートから投資で儲かるいい方法があると声をかけられた。カフェに友人と一緒に出向くと説明役の人がいて、USBを買って学べば株価指数の指標を使って先物取引で儲けることができるという。代金は約50 万円で、お金がないというと消費者金融で借りればいいと言われ契約書にサインした。その後、誘っていた友人とは別の友達が、この事業者とは関わらない方がいいと注意してくれ、消費生活センターを教えてくれた。解約するためには何をしていけばいいのか教えて欲しい。
(20 歳代:男性)
(3)保健・福祉サービス
相談事例3 友人に誘われて1000 円でサービスが受けられると店舗に行った際に契約したフェイスエステと化粧品の契約30 万円をクーリング・オフしたい。
昨日、フェイスエステに通っている友人に1000 円で体験できると誘われて店舗に出向いた。サービス後、フェイスエステと化粧品を勧められて自社割賦の契約書にサインした。印鑑を持っていなかったので書類は持って帰ってきている。化粧品は後日送るのでそれまで使うようにと試供品を貰って帰ってきた。店舗には3時間ほどいたので断りにくかったが、帰って来てやめようと思った。先程やめたいと連絡したら、電話で受付するのでクーリング・オフの書面はいらないと言われた。試供品は送り返して欲しいと言われたが、このままで大丈夫か。
(20 歳:女性)
(4)教養・娯楽サービス
相談事例4 高校時代の先輩から誘われ、裁定取引講座(注12)を契約。サラ金で借り入れ約80 万円を支払ったがクーリング・オフしたい。
高校時代の部活の先輩から「投資に興味はあるか」と勧誘され、隣市にある業者の事務所に連れていかれた。事務所内で、先輩を誘ったと言う男性から、「海外のスポーツゲームへの賭け事をやらないか。対戦するAチームとBチームどちらが勝っても儲かるように賭けるので損はしない。10 回の講座を受ければ賭け方が分かる」と言われた。約80 万円と高額だったが、「月に最大10 万円は儲かる。サラ金から借り入れてもすぐに取り返せる」と言われ、サラ金のATMのある場所を案内された。当日、ATMに出向いて約80 万円を借り入れ、事務所に戻り支払った。その後、1回目の講義を1時間受けた。本日、私を勧誘した先輩から「賭けても儲からないと判った。クーリング・オフするよう」と勧められた。
(20 歳:男性)
(5)レンタル・リース・賃借
相談事例5 賃貸マンションを退去するが、一か所しかキズをつけていないクロスの全面貼り替えを請求されている。家具を動かしたときにクロスの一部にキズがついてしまった。管理会社は契約書に記載があると言って、クロスの全面貼り替え費用約5 万円請求された。契約書を確認したが、管理会社の主張するような記載は見当たらず、不審に思っている。
(22 歳:男性)
- (注12) 市場間の価格差を利用して利益を獲得しようとする取引。
(6)金融・保険サービス
相談事例6 大学の友人に「ノーリスクで儲かる仕事」と言われ、説明会に行った。仕事をするためにはお金が必要と言われ、消費者金融で借りた。
大学の友人に「ノーリスクで儲かる仕事」と言われた。やってみると答えたら「1回説明会を聞きに行こう」と言われた。友人の車で行った。事務所のようだったがドアに看板はなかった。「アフィリエイター(注13)を募集する仕事。会社を立ち上げる。20 万円投資して」「一人紹介したら5万円入る。紹介した人がさらに紹介しても5万円入る」「ねずみ講でもマルチでもない」と言われた。お金がないと告げたら「消費者金融で借りれば。勤めていることにすればいい」と言われた。消費者金融で約20 万円借りた。一旦自分の口座にお金をいれて、通帳から振り込んだ。申込書など書類は何もない。実家の親が銀行の入出金の動きをみて、何に振り込んだか問いただされた。アフィリエイトの仕事だと告げた。父親はネット関連の仕事をしている。アフィリエイトでは儲からないと言われた。消費者金融で借りた分は親が返済してくれた。ノーリスクで儲かる仕事だと言われたが、嘘だと思う。やめたい。全額返金して欲しい。
(20 歳:男性)
(7)被服品
相談事例7 業者から自宅に電話があり来店を勧められたため行ったところ、長時間に渡りジュエリーの購入を勧誘され契約した。
女性の20 代と思われる担当者から自分宛てに電話があり、最初は世間話をしていたが「ブライダルセールをやっているので遠方の店舗まで来てくれないか」と誘われたので、暇だったので店舗に出向いた。店舗では担当者と上司の女性担当者の二人が対応し、最初は世間話や店舗のイメージについてのアンケートや彼女はいないのかなどを聞かれた。結婚に対する考えなどの話をされた時、良いジュエリーを身につけるべきだと言われ、商品を勧められ気に入った商品を選んだところ、契約書を出され記入させられた。記入後に選んだ商品の情報を書き込まれ、この時初めてクレジットの総額が60 回払いで約150 万円になることが分かった。
時間は既に午後8 時を回っており電車の時間も気になり、早く帰りたいので契約をしてしまった。クレジット契約の引落し口座は分からなかったので記入していない。記入して再度来店するよう言われた。帰宅後、高額な契約をしたことに不安となり契約解除したい。
(20 歳:男性)
- (注13) アフィリエイト(インターネットを利用した広告の一種。提携業者の商品広告を出し、その広告を見て商品購入を行った客の紹介料を得るもの。)を行うもの。
(8)食料品
相談事例8 数か月前、友人に頑張り次第で儲かると誘われサプリのマルチを契約したが解約返金して欲しい。どうしたら良いか。
友人2人に面白い話があるからとファミレスに呼び出されたので行ったところ、サプリメントのマルチをしないかと誘われた。既に2人ともやっていて、マルチの会社のこととか、仕組みとか、プランの説明をされた。そして、頑張りによるが稼げる、具体的には、まず自分が入会して、サプリを買って、次に誰かを入会させ、その人がサプリを買うと、購入金額の約15%が稼げる連鎖方式だと言われ、その時はできるかなと思い申込んだ。しかしその後、サプリの料金の支払先であるカード会社から何度も請求がきたので、仕方なくカード会社指定口座にATMからキャッシュカードを使い、現金振り込みしたが、よく考えるとやめたい。返金して欲しい。
(20 歳:男性)
(9)他の役務
相談事例9 結婚式場の契約をした二日後に解約を申し出たところ、会場と日を押さえたので申込金30 万円が必要と言われた。不審に思った。
ネットで結婚式場案内を見て出向いた。挙式予定日は連休の中日であり、良い日なのですぐに埋まると急がされ、1万円入金して契約。領収書と契約書をもらった。他の結婚式場に出向いて当該事業者の評判を聞くと、申込金30 万円は高額過ぎる等、あまり評判は良くなかった。急がされて契約したこともあり、契約した2日後にメールで解約を申し出た。担当者から、会場と日を押さえたのでキャンセル料30 万円は必要と回答があった。契約書は手元にないが、「今週中に申込金の残金を入金しないと契約はなかったことになる」と記載があったように思う。キャンセル料を支払う必要があるか。
(20 歳代:女性)
2 若年層への消費者教育の取組
以下では、学校における若年層への消費者教育の具体的な取組を紹介する。
(1)出前授業を活用した取組
消費者問題は、社会の進展等にあわせて多様化、複雑化が見られ、また関連する法令の改正等も行われているため、現状に即した消費者教育を行うことが難しいという性質を有している。
学校においては学習指導要領に基づき消費者教育が行われているところであるが、より詳細、最新の事例等を踏まえた教育を行うために、消費者問題に詳しい消費生活センター相談員やNPO等に出前授業を依頼する方法も考えられる。
事例1 関係機関などと連携した学校向けの出前授業の実施
(1)経緯
- 和歌山県県民生活課では、小学校、中学校、高等学校の子供が消費者トラブルに巻き込まれないために、和歌山県消費生活センターで出前授業を実施する一方、県金融広報委員会や消費者教育授業に実績を持つNPO法人と連携している。
(2)具体的な取組
- 消費者教育に関して、和歌山県消費生活センターでは相談事例を基にしたトラブルや契約等、県金融広報委員会では金銭教育、NPO法人では食育等を中心に行っている。これらの活動を知ってもらうため、県教育委員会を通して県内の小学校、中学校、高等学校に対して紹介するとともに、出前授業の募集を行っている。
- 授業内容は、各学校からの希望に応じたものとしており、小学校では食育、中学校では契約、インターネット、金銭教育などが多くなっている。
- 授業の際は、紙芝居やロールプレイなどの教材を活用して、いかに興味を持ってもらうか、いかに分かりやすく説明するかを心がけている。
- 例えば、小学生向けには、おやつや飲み物に入っている砂糖の量を当てるクイズで砂糖の摂り過ぎについて話をしたり、予算内で買い物をするワークショップを通じ物の選び方やお金の使い方を楽しく学習したりするなど、子供の年代に合わせた授業内容としている。
- 授業内容によっては、活用した教材を県内の振興局で貸出しを行い、教師が消費者教育を実施しやすい環境を整備している。
(3)効果
- 派遣する講師は消費者問題などの専門家であり、豊富な経験を活かして適切な内容を教えることができる。
- 派遣した講師の授業を見ることで、学校の教員が消費者教育を授業に取り入れやすくする。
(4)課題
- 毎年、出前授業の案内を行っているが、希望がなく講師を派遣できていない学校に出前授業の活用を促す工夫が必要である。
- 国の財政支援がなくなった場合は、すべての学校に講師を派遣することが難しくなる。
(和歌山県)
事例2 消費生活センター相談員の出前授業
(1)経緯
- 消費者教育について技術・家庭科家庭分野の教員が消費生活総合センターと相談した結果、詳細な専門知識を持った同センター相談員の出前授業を取り入れるのが良と考えた。
(2)具体的な取組
- 2年生の3学期に5時間の消費者教育を行っており、このうち、1時間を出前授業により、「契約について」、「さいたま市に多いトラブル」、「インターネット広告画面の間違い探し」について教えている。
- 出前講座の副教材として、さいたま市教育委員会から配布された同センターのパンフレットを使用している。
- 授業全体の内容は、物とサービス・家計(1時間)、契約からクーリング・オフまで(1時間、DVDを使用)、出前授業(1時間)、悪質商法(1 時間、DVDを使用、ロールプレイング)、消費者の権利と責任、クーリング・オフとまとめ(1時間)である。
(3)効果
- 出前授業に対する生徒の反応は良かったので、将来トラブルに遭った際の参考になると思う。
(4)課題
- 技術・家庭科家庭分野は3年間で87 時間あるが、そのうち、消費者教育には5時間しか割り当てられておらず、授業時間が不足している。
(さいたま市立春野中学校)
事例3 危険に関する出前授業
(1)経緯
- 危険学プロジェクトは、平成19 年よりボランティアで「自然と技術の関係に潜む危険に関する調査、実証研究」等を開始し、その中で「子どものための危険学」グループは、子どもの事故防止のための情報発信を行っている。
- 平成20 年に幼稚園児向けの絵本・冊子を作成し、幼稚園で先生に読み聞かせや粘土の実験を実施してもらった。平成23 年より小学校低学年を対象に1校で出前授業を開始し、平成27 年度には、10 校・団体に拡大して実施している。
(2)具体的な取組
- 小学校1年生の生徒(2年生の場合もある)とその保護者に体育館に集まってもらい、身の回りの危険について全体的な説明を行う。次に、15 人程度の4グループに分け、粘土を使った4種類の実験を順番に移動しながらすべて見せる。
- 具体的には、子どもの手と同じ大きさの「粘土の手」や、頭と同じ重さの「粘土の頭」を使用し、「粘土の手」を扉に挟んだり、「粘土の頭」を平均台の角にぶつけたり、椅子に座り後ろに傾けて倒れる想定で「粘土の頭」が潰れる様子を見せる等している。子ども達は大けがをして痛そうな危険について、実感をもって学ぶことになる。
- 次に体育館で、子どもたちに、普通のものでも、使い方・接し方次第で危険になるものを見つけさせる。「何を、どのようにすると、どのように危険なのか」を引率者に説明し、パネルに記入してもらうことで、自主的に危険を見つけることを学ばせている。
- 最後に、生徒に発表させて学んだ内容をみんなで振り返らせている。
(3)効果
- 生徒同士が注意し合うようになるなど、生徒の行動に変化が見られ、教員には好評である。
- 教育委員会の機関紙、校長OBのネットワークで紹介されることにより、出前授業数が拡大した。
(4)課題
- 多くの学校で土曜授業として実施して欲しいが、協力してくれるボランティアの人数に限りがある。
- プロジェクトが平成28 年度で終わるため、現行のボランティアメンバーだけでは3年程度しか継続の見込みがない。折角開発したプログラムなので継承していただけるところがあればありがたい。
(危険学プロジェクト)
事例4 生徒が関心のある出前授業を選択
(1)経緯
- 平成22 年度から24 年度までの3年間、神奈川県の「シチズンシップ教育(消費者教育)活動開発校」(注14)の指定を受け、主に消費者教育について研究を実施した。
- 過去、外部講師を招いて大人数の生徒が受講する講義を実施したが、受け身の学習になりがちなため、講義を聞いていない生徒が見られ、聞いている生徒の理解の度合いも様々であった。そのため、小規模の参加型のワークショップ形式の授業を行うこととした。
(2)具体的な取組
- 外部講師を招き、講演とあわせて生徒が参加するワークショップ型の授業とした(定員は20 人程度)。授業時間は90 分。
- 生徒には講座の分野を示し(模擬裁判、悪徳商法等14 講座)、自ら受講する講座を選択させた。
- 生徒に受講当日にワークシートを配布、翌日に提出させ、担任が成果を確認した。
(3)効果
- 小規模かつ、参加型の学習であり、生徒は講座に集中できた。
- 生徒が自ら講座を選択するため、講座に主体的に参加した。
- ワークシートを提出させることにより、生徒の理解度を把握することができた。
(4)課題
- 生徒にとって、講座の内容よりも、講座に参加して楽しかったという印象がより強く残る可能性がある。
(神奈川県立相模原総合高等学校(注15))
- (注14) 「シチズンシップ教育活動開発校」とは、神奈川県「県立高校教育向上推進事業」において教育委員会が設定したシチズンシップ教育をテーマに研究に取り組む高校を指定し、指定校がその取組と成果を普及・推進するもの。
- (注15) 当該校は、平成25 年度から27 年度までは神奈川県の「県立高校教育力向上推進事業ver.2」において「シチズンシップ教育」研究推進校の指定を受け、消費者教育については家庭科・公民等において行ったほか、カードゲームを利用したライフプランの学習等を行った。
(2)生徒参加型の取組
生徒の多くは未成年であり、詐欺等の悪質商法等の消費者被害は身近でない場合が多く、消費者教育について自身のものとして考えることが難しい場合がある。
そのため、生徒が自主的に授業に参加し、消費者問題を自身の問題としてとらえやすくするため、生徒が参加するロールプレイング型とする方法なども考えられる。
事例5 悪質商法のロールプレイング型授業
(1)経緯
- 平成22 年度から24 年度までの3年間、神奈川県の「シチズンシップ教育(消費者教育)教育活動開発校」の指定を受け、主に消費者教育について研究を実施(再掲)。
- 上記事例4の他、「家庭科」等の既存の教科等における消費者教育の充実も図った。
(2)具体的な取組
- 「家庭総合」の授業で、生徒に悪質商法の加害者あるいは被害者を演じるロールプレイングを行わせることにより、人はなぜだまされるのか人間心理を考えさせ、加害者にも被害者にもならないように指導した。
- 授業時間が一時限90 分と比較的長く設定されているため、教員からの説明、ロールプレイング、考察、指導を一貫して行った。
(3)効果
- 生徒自ら悪質商法の加害者側に立ち、その心理を理解することにより、生徒が被害に遭う可能性を減らすことができる。
(4)課題
- 生徒にとって悪質商法は身近なものではないため、授業の内容に対して実感がわかない場合もある。
(神奈川県立相模原総合高等学校)
(3)生徒に消費者問題について考えをまとめさせる取組
先のとおり、生徒にとって消費者被害は必ずしも身近なものでないため、消費者教育に対する生徒の関心が高くないことも考えられる。
そのため、消費者教育について、授業を聴くだけでなく、自らの考えをポスター等にまとめさせ、発表させることにより、生徒の関心を高める方法がある。
事例6 ポスター等の作成及び学外への発表
(1)経緯
- 生徒の学習効果を考慮し、家庭基礎(全70 時間、1年間)の期末テストが終わった1年生の3月に消費者教育を行うとともに、生徒がより関心をもって取り組めるよう自分の考えをポスター等にまとめさせ、外部に発信させることとした。
(2)具体的な取組
- 契約、クレジットカードに関するトラブル等に関してDVDを使って教師から説明した後に、なぜ消費者被害に遭うのか生徒に発表させた後、ポスターと標語にまとめさせる。授業時間は1時間。
- 優れたポスターは文化祭で掲示し、また優れた標語についても文化祭で配布するお菓子にシールとして貼っている。
(3)効果
- 多くの生徒は、自分が作ったポスター等を外部に発信することにより、消費者被害が減って地域が良くなればと思い、意欲的に取り組む。
(4)課題
- 多くの生徒にとって、消費者被害は身近なものではないため、消費者被害が起きる原因は何か、どうすれば被害が無くなるかというところまでは理解が達していない。
(5)その他
- 少ない授業時間を、3月の期末テストの後の時間や文化祭の時間を活用してカバーする工夫をしている。
(北海道札幌丘珠高等学校)
事例7 ポスターの作成、発表及び生徒の関心の高い教材の活用
(1)経緯
- 消費者被害は生徒にとって身近でないため、生徒が主体的に自ら考えるようポスターを作成させる授業の構成とした。また、教材は生徒の関心のあるものを使用するよう工夫した。
(2)具体的な取組
- 家庭総合(全140 時間、2年間)の中で、DVD教材を生徒に視聴させ、教員が内容を説明し、生徒に考えをポスターにまとめさせ、クラス内でお互いに発表させた。
- 授業時間は3時間。
- DVD教材は、10 分程度の長さで、内容がバランスよくまとまっているものを選んだ。また、地元の建物が映っているものを使用するなど、生徒が関心をもって取り組めるよう工夫した。
(3)効果
- 生徒が自ら考えをまとめ、発表することにより、知識が定着する。
- DVD等に生徒が知っているものが映っていると、親しみを感じて集中して見ることが期待できる。
(4)課題
- DVD鑑賞、教員からの説明の時間のほか、生徒のポスター作成、発表の時間が必要であり、相応の授業時間を要する。
(大阪府立芥川高等学校)
事例8 消費者に関連するキーワードを連想させ、知識の総合化に基づき文章化させる授業(注16)
(1)経緯
- 適切な消費行動をとるための基礎となる意思決定能力等を育むため、消費者に関連するキーワードを連想させ、キーワードを整理し、それを文章にまとめさせる授業を行うこととした。
(2)具体的な取組
- 9マスの表を配布し、中央に消費者に関連するワードを書き込み、その周囲のマスにワードから連想される言葉を書き込ませる。さらにその外側に設置した9マスの中央に連想された言葉を書き込み、同様に連想される言葉を書き込んでいくことでアイディアを広げさせ、そこからキーワードをトピックとして選び、200 字程度の文章を作成させる。
- 5から6名程度のグループを作り、作成した文書について1分で説明、討議を行いグループの代表者を決めた後、グループの代表者がクラス全体の前で発表し、自己評価・相互評価を行う。
(3)効果
- 読み手の興味を引く文章を書く工夫をすることにより、知識が総合化される。
- キーワードを文章化するためには論理的に考察することが必要であり、合理的な意思決定による消費行動ができる基礎能力が高まる。
(4)課題
- 生徒にとって消費者問題は身近でないため、最初のキーワードを考えさせる際に何が消費者問題なのかを考察させる必要がある。キーワードが思いつかない生徒もおり、指導者の丁寧なサポートも必要である。
(私立関西大学高等部)
- (注16) 詳細は、日本消費者教育学会関西支部「関西発!消費者市民社会の担い手を育む[改訂版]」p40 を参照。
(4)選択科目による詳細な消費者教育の取組
消費者問題は多様化、複雑化しているため、生徒の希望等を踏まえ、必修科目で教える内容以上の内容を教えたいという場合もある。そのような場合、選択科目において、より詳細な内容の消費者教育を行う方法がある。
事例9 経済選択科目での消費者教育
(1)経緯
- 消費者被害の防止のためには、より詳細な消費者教育を行うことが望ましいため、選択科目の「経済研究」(注17)において詳細な教育を行うこととした。
(2)具体的な取組
- 「政治・経済」において1時間程度、消費者教育を行っているところ、選択科目の「経済研究」において、3時間程度の詳細な消費者教育を行っている。
- 「政治・経済」の授業だけでは時間の関係で十分に取り上げることが難しい、クレジットカードの過度な利用により自己破産になるおそれがあること、悪質な商法にだまされないための対応方法等について自作のプリントを使って教えている。
(3)効果
- 生徒自ら科目を選択しているため、消費者教育に主体的に取り組む。
- 授業時間を多くとることで、詳細な説明が可能になり、生徒の消費者問題に関する理解を深めることができる。
(4)課題
- 選択科目であるため、生徒全員には詳細な消費者教育を行えない。
(北海道札幌丘珠高等学校)
- (注17) 「経済研究」とは「政治・経済」の経済分野を更に詳細に学習するための授業。
(5)特別支援学校における取組
PIO-NET に登録された相談データによると、国民生活センターと全国の消費生活センターに寄せられている知的障害者等の相談件数は増加しており、特別支援学校等による消費者教育の充実が重要と考えられる。
特別支援学校における消費者教育については、生徒にとって身近な事柄に関する専門家による出前授業といった方法も考えられる。
事例10 出前授業の活用
(1)経緯
- 卒業後の生徒の自立に向け取り組んでおり、生活を送る上で関係することの多い携帯電話に伴うトラブルや、身だしなみについて、専門的な知識を持っている企業の方を講師として招き、授業を行っている。
(2)具体的な取組
- 高等部で携帯電話事業者による出前授業(1時間から1時間半)を行っている。授業では、無料サイトから有料サイトへ誘導されることによるトラブル、アダルトサイト、デート商法によるトラブルなどを紹介している。
- また、化粧品等の販売会社による出前授業(2時間)では、ネクタイの締め方等の身だしなみに関して実演形式で教えているほか、化粧品、偽物のブランド品やライター等の高額品の訪問販売に関する注意点を教えている。
- 手元にあるお金を全て使ってしまう生徒もいるため、今後、金融経済教育の出前授業として、銀行口座の開き方、お金の振り込み方等を取り扱うことを予定している。
(3)効果
- 卒業後においても、トラブルに巻き込まれず、生徒が円滑に自立して生活出来ることを期待している。
(4)課題
- 消費者教育の教材について、特別支援学校の生徒にあわせた内容のものがあると良い。
(神奈川県立茅ケ崎養護学校)
(6)大学等における取組
ア 大学における消費者教育や啓発の取組大学入学後、一人暮らしを始める学生も多いため、多くの大学では、学生部等が企画する入学時のオリエンテーションの中で消費者被害に関する啓発や情報提供を行っているほか、一部の大学では教育課程内で消費者教育を実施している例も見られる。
事例11 大学の必修科目の中に消費者教育を組み込む(注18)
(1)経緯
- 学内に設けた学生相談室に悪質商法に関する相談があったこと、卒業生からの消費者教育について大学に要望があったこと等から、1年生の必修科目である「大学・社会生活論(注19)」の中に消費者教育を取り入れることとした。
(2)具体的な取組
- 学生生活・社会生活上の基本事項や、消費者の権利と責務、大学生に多い消費者トラブルとその対処方法などを教えている。
- 大学生に多い消費者トラブルとしては、架空請求メールなどの有料サイトのトラブル、マルチ商法、クレジットカードに関するトラブルなどがあり、これらへの対処法(トラブルに遭わないための心得、クーリング・オフ制度、未成年者契約取消等)とあわせて、トラブルに遭った場合の相談窓口について教えている。講義時間は90 分。
- 全クラスに対面での講義を行うことは他のカリキュラムとの関係で日程上厳しいため、一部の学類では視聴確認テスト付きのeラーニング教材を用意している。
(3)効果
- 講義後のアンケート(「どの授業内容が役に立ったか」「どの授業内容がわかりやすかったか」「どの授業内容の満足度が高かったか」)において、消費者教育の対面授業の受講者はどの設問に対しても高い評価をしているため、消費者被害に注意深くなること、被害に遭った際も適切に対処することが期待される。
(4)課題
- クレジットカードや海外でのトラブルをめぐる消費者教育が必要になりつつあるが、カリキュラムの関係のために消費者教育の対面授業を採用する学類が減少してeラーニングに移行する傾向にある。
(国立大学法人金沢大学)
- (注18) 詳細は「知的キャンパスライフのすすめ-スタディ・スキルズから自己開発へ-第4版」(学術図書出版)参照。
- (注19) 大学新入生が大学のあり方に慣れ、大学生らしい学習態度等を身につけて、充実した大学生活を送れることを目的とした科目で、1年生の必修科目とされている。具体的には大学生として必要なスタディ・スキルズ(例えば、ノートの取り方、資料整理の方法等。)の習得、学生の自己発見・自己開発を応援すること(金沢大学と協定を締結している海外の大学への派遣留学制度等)などを目的としている。
イ 消費者被害に関する冊子の配布
次の事例は、全国大学生協連合会の取組であり、各大学生協の「新歓冊子」、「機関紙」に活用されている消費者教育である。
事例12 大学生協の消費者被害のコラム集の配布
(1)経緯
- 大学の新入生は、大学入学により初めて親元を離れて自立した生活を送るなど社会との関連も深まり活動範囲も広がるが、社会的な経験が乏しいことから様々な消費者被害に巻き込まれる可能性が高い。また、在学生も20 歳になることにより、未成年者契約取消が適用されなくなり、成人として責任を負うこととなる。そのため、学生が安心・安全に大学生活を送れるように学生やその保護者に消費者被害について啓発する必要がある。
(2)具体的な取組
- 被害事例と対応策をセットにした消費者被害のコラム集のフォーマットを全国生協連が作成し、各大学生協がそれをベースに独自の消費者被害コラム集を作成し、新入生やその保護者向けの「新歓冊子」や在校生向けの「機関紙」に活用している。
- 消費者被害の例としては以下のようなものがあり、それぞれに数行のワンポイントアドバイスをつけて対処法を示している。
- ○アダルトサイトの相談が年間で10 万件!?
- ○プリペイドカードの購入を指示する業者には注意しよう!
- ○プロバイダ契約には注意しよう!
- ○約束の時間に来なかった引越し業者
- ○入居時にも部屋の確認を!
- ○街中でのキャッチセールス
(3)効果
- 学生やその保護者が、消費者被害について適切に対処できるようになる。
(4)課題
- 文書などでの広報に加え、対面での説明や相談をどのように増やしていくか。
(全国大学生協連合会)
第3 若年層の消費者教育に関する調査
1 学校における消費者教育に関するヒアリング
(1)ヒアリング調査
消費者教育は学習指導要領などに基づき、学校等で行われている。特に平成20 年及び21 年の学習指導要領の改訂の際に、社会科、家庭科などの教科を中心に消費者教育の充実が図られている(注20)。しかしながら、詐欺等の消費者被害はこれらの学校の生徒(注21)や学生にとって年齢の点などから身近なものではない場合もあり、教えられた内容が必ずしも十分に受け止められていない可能性もあるのではないかと考えられる。
そのような観点から、大学及び大学院(以下「大学等」という。)の学生に対して、これまでに受けてきた消費者教育、印象に残っている授業内容などについてヒアリングを行うことにより、学校における消費者教育の実態について調査を行った。
(2)ヒアリング項目及び回答の概要(注22)
ア 消費者教育のイメージ
「消費者教育」という言葉についてどのようなことが思い浮かぶか調査を行ったところ、具体的なイメージがつかみにくい、消費者教育で学ぶ内容は知っておくべきであるが、知らないことが多い、詐欺などの被害に遭った際の対処方法を教えてもらうものという回答が多かった。
イ これまでに受けてきた消費者教育
現在通っている大学等において消費者教育を受けたことがあるか、過去に小学校、中学校、高等学校で消費者教育を受けた経験、印象に残っている授業やその理由、どのような分野の消費者教育を受けたかったか調査を行った。
- (注20) 平成20 年及び21 年の学習指導要領改訂については、本報告書P.8を参照。
- (注21) この章において「生徒」とは、他に規定するものを除き、学校教育法の生徒及び児童をいう。
- (注22) ヒアリングの詳細については、参考資料1参照。
マル1 現在通っている大学等における消費者教育
入学時のオリエンテーションで、部屋の賃貸借、マルチ商法等に関する資料を配布されたが、内容はあまり覚えていないという回答が多く聞かれた。一方、金融会社の社員等が臨場感をもって行った授業には興味を持って聞くことができたという回答もあった。また、1年生の時に消費者教育に関係する科目を履修した結果、消費者教育に興味を持ち、2年時以降、専門的に学んだという回答もあった。
マル2 小学校、中学校、高等学校における消費者教育
消費者教育について習った記憶はあるが、具体的な内容については覚えていないという回答が多く聞かれたが、社会的に大きな消費者問題があり、その内容について授業で取り扱ったもの(注23)については、よく覚えているという回答も聞かれた。
マル3 印象に残っている授業とその理由
警察の人など外部の人による授業は、校内の教職員と違う人に教えてもらうため印象に残るという回答があった。また、教職員が自身の消費者被害をもとに行った授業について、生徒にとって身近な人のトラブルのためか、印象に残っているという回答があった。なお、いずれの場合であっても、詳しい内容までは覚えていないとのことであった。
マル4 受けたかった消費者教育の分野
学生になって、初めてクレジットカードを作る、部屋を借りるという経験をするため、これらの契約をする前にクレジットカードの仕組みや契約について知っておけば良かったという回答があった。また、消費者トラブルに遭った際に相談できる窓口について教えて欲しかったという回答があった。
- (注23) ヒアリングをした学生によると「平成20 年頃の冷凍餃子により健康を害した事案に関連して、製造物責任法(平成6年法律第85 号)について授業を受けた。」とのことであった。
ウ 消費者事故・トラブルに遭った場合の対処等
ヒアリング対象者、あるいは親類や友人が消費者事故等に遭った場合の対処、トラブルにあわないために気を付けていること等について調査した。
マル1 トラブルに遭った経験の有無と対処
架空請求、プロバイダ変更に伴うトラブルなどに遭ったという回答があったが、自分で対応したり、家族の助けで解決しており概ね被害を未然に防いでいた。
例えば、プロバイダ変更に伴うトラブルでは、同居する祖母名義で契約されていたプロバイダを祖母が変更した結果、利用料金が変更前より高額となったため解約を申し入れたところ、プロバイダから解約料がかかると言われたが、学校でクーリング・オフという言葉を習った記憶があったため、家族とも相談し、クーリング・オフを申し込んだところ、解約料なしで解約ができたとのことであった。
なお、一部ではあるが被害を受けた事案もあった。具体的には、親類がSNS(注24)のユーザーID を乗っ取られ、当該親類のID を使って電子マネーの購入と購入した電子マネーのID を教えて欲しいとの依頼をされたため、電子マネーのID を教えてしまい、その結果、お金を取られたというものである(注25)。
マル2 トラブルに遭わないために気を付けていること
通信販売サイトについて、販売事業者の連絡先等をチェックする、バナー広告をクリックして移動したサイトは信用せず、正規のサイトから注文するようにしている、怪しいと思われるサイトにはクレジットカードの番号を安易に入力しない等、インターネット関係のトラブルについて気を付けているという回答が多かった。
- (注24) ソーシャルネットワーキングサービス(Social Networking Service)の略で、登録された利用者同士が交流できるWeb サイトの会員制サービスのこと。
- (注25) 被害者は、お金を取り戻すことは難しいと考え、警察などには相談しなかったとのことである。
エ 今後受けたい消費者教育等
消費者教育について、今後受けたい消費者教育の分野、どのような方法であれば消費者教育を受けやすいか等について調査した。
マル1 今後受けたい消費者教育の分野
大学卒業後の生活や将来的なことを念頭に、税金、一人暮らしに必要な光熱費等の額を知りたいという回答や、特定保健用食品(トク ホ)のマークなど生活に関係する商品等のマークについて知りたいという回答があった。また、通信販売を利用する機会が多いことから、サイトの利用規約の内容が分かるような教育を受けたいという回答があった。
マル2 受けやすい消費者教育の方法
消費者トラブルの事例や解決方法がまとめられたサイトがあれば時間がある時に勉強できる、年齢にあった内容の教材があれば良かった、大学で消費者教育の集中講座があれば受けてみたいという回答があった。
オ 消費者教育を行う時期・方法
消費者教育の内容は、小学校、中学校、高等学校で教えてもらっても難しいと思うが、クーリング・オフ等の言葉を少しでも覚えていれば、将来トラブルに遭った時の役に立つので、消費者教育は、継続的、定期的に行うことが大事ではないかという回答が多く聞かれた。
カ 消費生活センター
消費生活センターを知っているという回答が多く聞かれたが、消費生活センターには、被害額が高額でないと相談してはいけない、気軽に相談できないという印象があるという回答が多かった。
また、同センターに相談しようと思い検索してみたところ、多数のセンターとその電話番号が表示され、どこに相談して良いか分からなかったため、結局、相談しなかったという回答もあった。これは、「188(消費者ホットライン)(注26)」の周知が必ずしも十分ではないことを示していると思われる。
- (注26) 3桁の電話番号であり、当該番号に電話をかけると、全国共通の電話番号から身近な消費生活相談窓口を案内するもの。
キ 成年年齢引き下げについて
成年年齢を20 歳から18 歳に引き下げる議論が見られることから、成年年齢引き下げに対する感想等について調査したところ、18 歳は大学入学、就職、初めての一人暮らしなど、環境が大きく変わる時期であり、現在の成年年齢の20 歳までの2年間に未成年者という立場でいろいろな経験をすることができるので、いきなり18 歳で成人とされると消費者被害が増えるのではないかという回答や、成年年齢を引き下げるのであれば、事前の消費者教育を充実させることが重要ではないかという回答が多かった。
一方、消費者教育を適切に受けた人で、かつ、保護者から早く自立したい人にとっては、18 歳を成年年齢として欲しい人もいるのではないかという回答も一部あった。
2 ヒアリング結果(まとめ)
以上のヒアリング結果を踏まえると、消費者教育には以下のことが重要と思われる。
(1)継続した教育
消費者教育は、関連する言葉を覚えていれば消費者被害に遭った時に適切な対応を取れることが期待できることから、小学校等の段階から継続的に繰り返し行うことが重要と考えられる。また、高校卒業等により一人暮らしを始めること等により消費者被害が身近となり、消費者教育に関心が高まる場合もあるため、卒業後であっても大学や職場など様々な場において消費者教育を受けることが望ましい。
(2)教育の内容
スマートフォン等が広く個人に普及する中で、インターネットを利用したトラブルや犯罪に巻き込まれる被害者の低年齢化が進んでいることから、インターネットの適切な利用等、児童生徒の発達段階に応じた情報モラル(注27)教育の一層の充実が求められる。また、高校卒業後の大学入学や就職等の大きな環境変化への対応、成年年齢引き下げの議論を踏まえると、賃貸借等の契約の基礎知識、クレジットカードの仕組みなどについては、高校卒業までに学校で教えることが望ましいと思われる。
- (注27) 情報モラルとは、小学校学習指導要領解説において、「情報社会で適正な活動を行うための基になる考え方と態度」であり、「他者への影響を考え、人権、知的財産権など自他の権利を尊重し情報社会での行動に責任を持つことや、危険回避など情報を正しく安全に利用できること、コンピュータなどの情報機器の使用による健康とのかかわりを理解することなど」としている(中学校、高等学校においても、生徒の発達段階を踏まえ同様に指導することとしている。)。
(3)消費者教育を行う際の留意点
消費者教育を行う際は、生徒にとって身近な事案(注28)や、社会的に関心の高いものであれば生徒も興味をもって授業を聞くことが期待できるため、こうした点についても留意することが望ましい。教材(副教材を含む。)についても、生徒の直面する被害の実態等を踏まえたものとすることにより、生徒の関心を高めることが期待できると思われる。
(4)消費者被害に遭った場合の対応
消費者被害にあった時の相談先や、相談先の具体的な利用方法などを知っていることも重要と考えられるため、「188」や、消費生活センターで実際に受けている相談などを消費者教育の内容に盛り込むことが考えられる。
- (注28) 同世代の生徒が被害に遭っている事例や、卒業後の自分の生活に関係のある事柄(就職後の税金の支払い、一人暮らしを始める際に気を付ける点(生活費、敷金・礼金、隣人とのトラブル等))などが考えられる。
第4 コーディネーターの活用による学校における消費者教育の充実
若年層に対する消費者教育は、第3で述べたように、学校における教育が重要と思われる。一方、学校の教職員は一般的に勤務時間が長く(注29)、これまで以上に長い時間を消費者教育にあてることは困難な場合があることも考えられる。
消費者教育をより効率的、適切に行うためには、消費者教育を担う多様な関係者との連携等が望まれるが、教職員自らがその役割を担うことは、前述のとおり時間的な問題もあり、難しいと思われる。
そのため、消費者教育専門のコーディネーター(注30)による関係者間の連携の促進等(注31)によって学校における消費者教育の一層の充実を図ることも考えられる。
以下、コーディネーターの取組等について記述する。
- (注29) 「OECD 国際教員指導環境調査(TALIS2013)」によると、日本の教員(中学校及び中等教育学校前期課程の校長及び教員)の1週間当たりの勤務時間はOECD 参加国最長(日本53.9 時間、参加国平均38.3 時間)とされている。
- (注30) コーディネーターについて、「地域連携推進小委員会取りまとめ」(平成27 年3月消費者教育推進会議地域連携推進小委員会)では「コーディネーターは、担当地域における日々の消費者教育を実践面・実績面において全般的に企画・調整し推進する。消費者教育の拠点等で、地域全体の消費者教育の実践を支援する専門職として…環境の整備などを担う。」とされている。
- (注31) コーディネーターの役割として、関係者間の調整のほか、地域の実情に合った独自教材の作成、各学校にあった教材の紹介、学校教職員に対する消費者教育なども考えられる。
【岡山県消費者教育コーディネーター(注32)】
(1)設置の経緯
- 「岡山県消費者教育推進計画」(平成26 年3月)において、県の消費生活センターを消費者教育の拠点とし、消費者教育を推進するコーディネーターを配置することとされた。
(2)主な活動内容等
- 岡山県消費者教育連絡協議会(注33)等により、市町村・教育委員会等とコーディネートした学校における出前授業、教員研修や、大学教授や小学校の教員等と連携した教材の開発。
- 教育委員会の「子ども応援人材バンク」(注34)に登録し、講師を依頼された出前授業のコーディネート。
- 活動に当たって、学校現場は忙しいため、消費者教育だけに時間を割いてくれることは困難であることに共感する必要があり、学校が求めることを把握し、教育委員会にお願いしたいことを具体的に示すよう留意している。
(3)設置の効果
- コーディネーターを設置した平成26 年度以降、下表に示したように教員向け消費者教育講座の参加者、消費生活センターの生徒・学生対象啓発セミナーの回数・参加人数、開発教材数のいずれも平成25 年度以前より増加している。
- 消費者教育教材作成には、新たに大学教授や教員、教育委員会(県・市)などの参加が得られた。
| 年度 | 平成23 | 平成24 | 平成25 | 平成26 | 平成27 |
|---|---|---|---|---|---|
| 教員向け消費者教育講座(人) | 8 | 18 | 10 | 68 | 37 |
| 生徒・学生対象啓発セミナー (回) (人) |
11 1861 |
12 1917 |
14 1565 |
18 2787 |
17 3230 |
| 消費者教育教材作成 (冊) | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 |
- (注32) 詳細は参考資料2参照。
- (注33) 岡山県における消費者教育に関する行政機関等の連絡調整及び協議を行うため、平成18 年6 月に設置。毎年担当者会議を開催し、連携を図り教育計画等の進捗状況調査を行っている。岡山県の教育行政関係課、消費者行政関係課の他、金融広報委員会等により構成されている。
- (注34) 岡山県教育委員会において、子どもや学校への支援の充実を図るため、「企業や団体などの専門性を活かした支援が欲しい」、「こんな専門的な人に協力して欲しい」等の学校のニーズに応じて支援する企業等を「子ども応援人材バンク」に登録し、ホームページで公開している。
【千葉県柏市消費者教育相談員】
(1)設置の経緯
- 平成4年度に施行された学習指導要領に消費者教育が盛り込まれ、消費者行政からの積極的な支援策が望まれるようになったことを受け、平成3年5月に、学校における消費者教育を推進するため、「柏市消費者教育推進連絡会要領」を制定し、柏市消費者教育推進連絡会(注35)(以下「連絡会」という。)を設置。
- その後、より充実した教員による消費者教育実践への支援を進めていくため、平成7年5月に「柏市消費者教育相談員規則」を制定し、教職経験者を消費者教育相談員として委嘱した。
(2)主な活動内容等<本年度の予定>
- 連絡会の実施(年3回)による教育委員会、学校及び消費生活センターの連携強化の促進
- 柏市版消費者教育の体系イメージマップ(案)の作成について
- 柏市消費者教育推進基本計画(案)の作成について
- 柏市消費者教育ポータルサイト関連業務について
- 啓発資料の作成について
(3)設置の効果
- 平成18 年度から27 年度までの期間において、委員が自校で消費者教育の実践授業を48 本実施した。また、当該内容を「消費者教育授業実践事例集」(これまで5冊発行)として取りまとめ、学校に配付するとともに、柏市消費者教育ポータルサイト等に掲載をし、周知を図った。
- 消費者教育相談員の設置により、学校における消費者教育の推進(例:教育委員会との連携)を図るシステムを確立することができた。
- (注35) 学校での消費者教育を支援、推進するための連絡会。柏市内の小中高学校の教員及び教育委員会の教育研究所長等から構成されており(委員数は10 数名)、事務局は消費生活センターとされている。連絡会の主な事務を消費者教育相談員が担当している。
第5 提言
当委員会では、若年層を中心とした消費者教育についてヒアリング等の調査を行ってきた。
調査において、当委員会本会議の場で、有識者より学校における消費者教育に関する実態調査の重要性についての意見が聞かれた(注36)。今後の消費者教育の実施に当たっては、まずはこれまでの消費者教育の効果等を検証するための調査を行うことが重要と思われる。
また、18 歳や20 歳といった就職や大学入学等による環境変化、成年年齢に達する時に相談件数が増加する傾向が認められること(第2 1)、学生へのヒアリングの結果(第3)や、成年年齢の引き下げに関する議論が行われていることなどを踏まえると、20 歳になる前の段階も含め、当該世代のニーズに応じた消費者教育を行うことが重要と思われる。
さらに、消費者教育は家庭で行うことも重要と思われるが、共通して身に付けるべき知識に係る適切かつ体系的な消費者教育については、特に学校において行われることが重要と思われる。学校において消費者教育を行う際には、消費生活センター等の関係機関との連携により、一層、効果的な教育が行われることが期待できるため、関係機関をコーディネートする役割を担う人材が重要と思われる(第4)。
以上を踏まえ、当委員会として以下の提言を述べるものである。
当委員会としては、関係行政機関において本提言を踏まえ、適切な措置を講ずることを求める。
1 消費者教育に関する実態調査の実施
国は、これまで、消費者教育について、平成元年の学習指導要領改訂の際にこれを学校教育に取り入れ、また、平成24年には消費者教育推進法を制定するなどして、その推進を図ってきた。
この間、文部科学省による全国の教育委員会及び大学等を対象とした消費者教育への取組状況調査や、地方公共団体レベルでの消費者教育に関する実態調査は行われているものの、国民全般を対象として全国的に行った消費者教育に関する調査は、内閣府(国民生活局)が平成20年2から3月に行った平成19年度国民生活選好度調査(平成21年2月公表)を最後に行われていない。
今回の調査において、当委員会が在学中の学生から過去に学校等で受けた消費者教育についてヒアリングをしたところ、授業で習った記憶はあるが、具体的な内容は覚えていないという者も多い(「第3 若年層の消費者教育に関する調査」参照)。
以上のことから、消費者庁は、文部科学省等の関係行政機関と調整の上、全国レベルにおいて、これまでの取組により、若年層の消費者の知識、意識及び行動にどのような変化が生じたとみられるか、また、消費者教育の課題を明確にし、今後の消費者教育の推進に生かしていくべきである。
なお、この実態調査を行うに当たっては、以下の点について可能な限り留意されたい。
マル1 これまでの消費者教育により、国民が消費者問題等に関する知識をどの程度身につけているかだけでなく、その知識に基づき取った行動内容についても把握すること。
マル2 今後の消費者教育の具体的な方策について検討するため、これまで消費者教育として行ってきた各種の方策がどのような効果を上げているかを明らかにすること。
- (注36) 第 217 回消費者委員会本会議において、静岡大学色川教授より「例えば、生徒がどのぐらい身に付いたのか、あるいは学生でもそうですが、その辺の評価ができるような調査でもいいのですが、そういうことが必要ではないかと考えます。(中略)2001 年に内閣府がした以来、学校における消費者教育の実態調査は全国的にされていないので、一度、きちんとする必要があるのではないかと思います。」との発言があった。
2 若年層の消費活動や消費者問題を踏まえた消費者教育の実施
多くの若者が高校を卒業し、就職や進学などで生活環境が大きく変わる18歳頃を境に、本人が身に付けている必要があると思われる消費者問題に関する知識も変化すると考えられる。
「第3 若年層の消費者教育に関する調査」でみたように、当委員会がヒアリングを行った学生からは、消費者教育として知りたいこととして、クレジットカードの仕組み、契約に関する事柄、消費者トラブルの相談窓口、特定保健用食品(トクホ)のマークなど生活に関係する商品等に付けられているマークなど、多岐にわたる回答があった。
このため、消費者庁及び文部科学省は関係行政機関と調整の上、18歳前後の消費者が直面する消費者問題の実態や、同年代の消費者における消費者教育に対するニーズに応じた消費者教育を実施すべきである。
3 コーディネーターの設置・活動の促進
学校における消費者教育については、教職員以外の者に消費者教育に関する授業(いわゆる「出前授業」)をしてもらいたいが、適当な者に心当たりがないため行えないとか、関連する教材があるものの教職員等に対する情報提供が不十分なため、教育現場で活用されていないなどの課題がある。
これらの課題は、関係者間を調整(例えば、学校の希望を把握し、それに見合う専門家を紹介等)したり、教職員に対し必要な情報を提供したりすることができるコーディネーターを配置し、これが機能することで解消されると考えられる。
基本方針では、コーディネーターを消費者市民社会形成の推進役としての重要な役割を果たす者と位置付け、消費生活センター等が拠点となりこの育成に取り組むこととしているが、現在、このようなコーディネーターを設置しているのは、11都道府県78市区町村等にとどまっている(平成27年4月1日現在)。
この背景として、学校の授業その他の教育活動において消費者教育の実践的な推進役としてコーディネーターの役割を担える資質を有する者が不足していることや、地方公共団体のコーディネーターの役割及び必要性に対する理解が不十分であることなどが考えられる。
現在、コーディネーター的な役割を果たしている人材についても、その位置付けが不明確であるため、十分に活動できていない可能性が考えられる。
以上を踏まえ、消費者庁及び文部科学省は、それぞれ以下について取り組むべきである。
(1)消費者庁は、地方公共団体においてコーディネーターの設置が促進され、その活動を充実させるため、必要な支援を行うこと。
具体的な支援としては、
- マル1 消費生活相談員、元教職員、元行政職員、消費者団体・NPO法人・民間企業で消費者教育に携わっていた者等の幅広い分野から人材を求め、その者に対してコーディネーターとして活動するために必要な研修を実施すること
- マル2 コーディネーターの育成に有用な教材を作成・配布すること
- マル3 コーディネーターが活動していく上で参考となるよう、先進的な活動事例集を作成・配布したり、コーディネーター同士が交流できるような機会を設けること
などが考えられる。
(2)コーディネーターがその役割を果たすためには、当該地方公共団体の消費者行政担当部局や学校又は教育委員会の意向を的確に把握する必要がある。このため、消費者庁及び文部科学省は、コーディネーターが消費者行政担当部局だけでなく、学校又は教育委員会とも意思の疎通が容易に図れるよう取り組むべきである。具体的には、地方公共団体に対し、コーディネーター、消費者担当行政担当部局、学校等の関係者を構成員とする会議の開催等、関係者間の連携が図られていると考えられる事例の周知などが考えられる。
(3)コーディネーターが十分に活動するためには、コーディネーター個人の資質・活動だけに頼っていたのでは限界がある。このため、消費者庁は、地方公共団体がコーディネーターの役割を十分に理解し、コーディネーターが継続的に活動できるよう、地方公共団体内の役職としての位置付けを明確にするよう取り組むべきである。
【今後の展望】子供・若年層に焦点を合わせた消費者教育
1 若年消費者の支援と保護
従来、消費者政策の課題は、どちらかと言えば、高齢消費者の財産被害・身体的危険からの保護や見守りの問題が重要な課題とされ(現在でも問題は大きい)、消費者教育に関しても、高齢消費者を念頭に置いた消費者啓発に重心が置かれる傾向にあった。しかし、翻って考えてみると、相対的に弱い立場にある「傷つきやすい消費者(vulnerable consumer)」には、高齢者のみならず、児童や少年さらには若年者層が存在する(ほかに「障害者等」もあるが、ここではひとまずおく)。成長期にある若年者は、知識や社会的経験が乏しいためにトラブルに巻き込まれやすく、身体的にも成人のような体力がないために思わぬ事故に遭遇することがある。
この点は、ちょうど高齢者問題とパラレルに語ることが可能であり、その差は、「衰退途上」か、「成長途上」かという点にあるに過ぎない(もちろんこれに尽きるわけではない)。
とくに、小さな子供が、歯ブラシを咥えて転倒し口内を損傷したり、スタンプ状トイレ洗浄剤を口にすることもあれば、こんにゃくゼリーの嚥下障害による窒息事故に遭遇することや、商業施設内の遊戯施設のエアボールで遊んでいる最中に骨折事故を起こすといった安全面での問題は少なくない。
また、少し成長すると、スマートフォンでインターネットを利用して個人情報を安易に入力して被害に遭ったり、オンライン・ゲームなどで思わぬ課金を背負い込むなどということもある。高校から大学にかけては、アポイントメントセールス、サクラサイトや異性紹介や投資勧誘、マルチ販売など、宗教まがいの不当勧誘、さらに手口の込んだ詐欺的勧誘行為などにさらされ、耐性がないばかりに被害に直面する若者がいる。そればかりか、中には、自らが加害者となってしまう者さえ現れる。
従来、高齢者に比して、未成年者・若年者は、まとまった財産を有しないことが多いために、欺瞞的取引のターゲットになる可能性は小さく、専ら、安全面での配慮の必要が中心に考慮されてきたが、今日では、必ずしも財産的被害からも無縁ではなくなっている。
未成年者に関しては、古くから保護の必要性が認識されており、民法でも「未成年者取消権」が認められていることは周知の通りである。わが国でも、これまで成年年齢が満20 歳とされ、成年に達しない未成年者については、原則として「制限行為能力者」として取消権が認められている(民法5 条2 項)。しかし、選挙権年齢の引き下げにともない成人年齢も18 歳に引き下げられるようになると、高校卒業前後から完全に独立した契約上の責任を自ら負うことが考えられることから、一層、若年層に対する配慮が必要となる。若年消費者に対する消費者教育が重要な課題となるゆえんである。
2 若年消費者にとっての消費者教育とは
第1 に、成長途上にある若年者は、概して好奇心が旺盛であり、経験を積み重ねながら知恵を身につけていくべき存在でもある。したがって、危険なもの(物・者)から遠ざけ、隔離し、保護するというだけでは十分でないことは明らかである。一方でセーフティ・ネットを張りつつ、物の危険や社会の危険に目を向け、そこでの危険を理解して回避の方法を身につけることができるようにすることが大切であるように思われる。
このことは、ナイフや包丁、ガスの点火装置など、日常生活に必要な器具の利用を考えれば容易に理解されよう。物的・社会的危険との接点に安全な形で触れさせることが必要な場合があることを理解しておかねばなるまい。食品についても同様で、自ら、腐敗臭や不適切な味などから身を守る術も身につけていくことが望ましい。
第2 に、若年者は、概して社会的な経験に乏しいことから、問題の具体的なイメージが困難であることにも配慮する必要がある。これまで、小遣いの範囲で日用品や食物を手に入れる程度の取引経験しかない若年者(子供)に、いきなり金融・投資に関するリスク情報を提供しても、ほとんど実感をもって理解することは期待できない。それだけに、若年消費者に対する消費者教育における素材の選び方には、慎重な配慮が必要であるように思われる。金銭教育一つをとっても、金銭の価値や使い方の工夫から始まって、段階をおってカードの利用などへと進めて、金融・投資・保険などの情報の提供を行う必要がある。また、その世代にあった問題・話題を選んで、効果的に提供することが求められよう。たとえば、包茎手術や美容整形での消費者問題、デート商法における留意点などは、高校生にはふさわしいかもしれないが、小学生には不適切である。その前提として、消費者教育に利用できる多様な教材が用意され、選択可能な形で存在していることが望ましいことは言うまでもない。
第3 に、子供は大人に学び、大人を真似て成長する。その意味では、若年者が何かを相談したいと考えたときに適切なアドバイスを与えられる環境を整えておくことと、周囲にいる大人が賢明な消費者としての知識を身につけて行動していることが重要である。若年に対する消費者教育を語ることは、その周囲にいる者の消費者力を高めるための消費者教育を語ることと連動していなければなるまい。今日の消費者問題が日々変化し、複雑化している現状を考えると、専門家の力を借りつつ、周囲の者が情報や問題意識を共有することも重要であり、その意味では子供たちと共に学び、考え、行動していくことも重要である。
3 若年消費者教育の主体・担い手
若年消費者を育て上げることは、第1 次的には、両親を始めとする保護者・家庭の社会的責任であろうが、そればかりではなく、仲間たちと多くの時間を過ごす学校の教育現場や職場などにも広がっており、最終的には国の責務でもある。これは、高齢者に対する見守りネットワークの構築と同様の問題である。
とくに、学校教育の現場は、将来において自立的かつ安全に生活していく人間力の基礎を涵養する場でもあるから(教育基本法5 条2 項参照)、家庭教育と並んで重要な消費者教育の場とならねばならない。考えようによっては、受験知識の習得以上に、消費者力を養っておくことは重要である。また、この学校教育と家庭を結びつけるにはPTA の果たすべき役割も大きい。
その際、消費者問題について詳しい者と、こうした、主体間を結びつける、コーディネーターの存在も、消費者教育を効果的に進める上で重要である。
学校教育の現場では、残念ながら、「消費者教育」がまだまだ正面から必要な教育内容として受け入れられていない場合が多いように見受けられる。若年者に対する消費者教育が市民権を持ち、とりわけ学校教育の中での全体的底上げを図るには、組織だった対応が必要である。一部の教師の貴重な努力は存在するが、それを一般化するには、具体的に、どの段階で、如何なる教材を用いて、何を学ばせるかを明らかにしていくことが必要である。同時に、若年者が、主体的に問題と取り組めるような、体験型の教育が求められよう。
4 やがて来る「消費者市民」のために
若年者に対する消費者教育の充実は、将来の力強い「消費者市民」を育てあげることにつながる作業である。「子供の貧困」や「ワーキング・プア」が話題となるような社会にあって、若年層を支え、賢明な消費者に育て上げ、消費者被害から自らを守るとともに、社会や環境にも配慮できる力強い消費者市民を育て上げることは、おそらく経済政策以上に重要な国家的課題であるように思われる。若年者は、純粋で行動力があるだけに、きちんと理解さえすれば、消費者問 題に対しても驚くほど実践的になる可能性を秘めている。
本報告で紹介された様々な取組みを参考に、学校教育における消費者教育の全体的底上げを図り、充実した若年消費者教育が追求されることを心から期待したい。若年消費者に対しても、エールを送りたい。
(文責 消費者委員会委員長 河上 正二)
【今後の展望】消費者教育に市民権を
教える教育から共に学ぶ教育へ
若年層を中心とした消費者教育について大きな障害となっている1 つ目は、情報化、国際化、ハイテク化の進展が目覚ましい今日において、保護者や教師の知識が追いつかず、保護者や教師が常に最新の情報を踏まえて教えることが困難な場合があるということである。日々、経験しなかった取引形態や新しい商品が出現し、新たなトラブルを引き起こしている。また、取引ルールや法整備も後追いとなり被害が常態化している。しかも、その状況は取引関連のみならず、食品表示や環境問題の変化など生活全般に及ぶ。
このような現状では、これまでのように保護者や教師は指導するという立場だけでなく、共に学ぶ立場という発想も重要と思われる。消費者問題について情報入手に努め、分かりやすい教材研究に日々取り組んでいるNPO などの専門家の積極的な活用も考えられる。
研究され実践を繰り返しブラッシュアップされた参加型の分かりやすい消費者教育の講座を共に受講することが効果的である。そして、その知識を共有化し、今後の生活で子ども達と共に考え行動していくことが重要である。
消費者問題は日々変化するので知識を得ることよりはむしろ、自ら考え、行動できる人間になることが大切で、疑問やトラブルがあった場合の相談窓口などへ進んで相談できる人間になることを目標とすべきである。そのためには、学校現場では出前講座を活用する、その出前授業を保護者参観にする、PTA 向けの子どもの消費者教育を体験する講座や親子講座を開催することなども有効だと考える。
覚える教材から参加型の教材へ
また、教師向けや保護者向け解説のついた教材も必要である。学校では出前講座で行った授業が継続的に学校で実施されるためには、出前講座と同じ内容の授業がすぐに実施できるような講師の解説書付き教材が必要である。
また、家庭向けの学習した内容が一過性のものにならないように、家庭での実践につながるお土産教材のようなものが必要である。家庭では、読み聞かせができる年齢では保護者向け解説書がついた絵本、一緒に遊べる年齢では保護者向け解説書がついたすごろくやかるた、家族の一員として協力できる年齢では保護者向け解説書がついた「食事をつくってみよう!」「洗濯をしてみよう!」など実践のガイドブックなど発達段階に応じて親子で学び家庭での実践につながるような教材が必要である。希望者が簡単にアクセスしてタイムリーな情報を得ることができる分かりやすい動画等を利用した教材も必要である。
消費者教育に市民権を
若年層を中心とした消費者教育について大きな障害となっている2つ目は、消費者教育という言葉が必ずしも十分に市民権を得ていないことである。今回実施されたヒアリングにおいても習った記憶はあるが内容は漠然としているという回答が多かった。これは消費者教育がまとまった教科ではなく、家庭科や社会科で単発的に扱われることも一つの要因と考えられる。消費者教育を習っているという意識を高め、小学校から発達段階に応じてスパイラル方式で復習しながら内容を深めていくことが期待される。大学では必修科目などとすることで、学生の受講を促し、消費者問題に適切に対応できるようにすることができると思われる。教員免許更新講座などにおいては消費者教育の受講を促すことも考えられる。保護者に対してもPTA の学習会などで消費者教育を行うことで、保護者と子どもが一緒に話し合う機会が増えるのではないだろうか。特別支援学校に対しては生徒の特性に応じた丁寧な消費者教育を生徒、保護者、教師向けに実施することが大切だろう。また、新社会人は社会経験が浅く消費者被害に遭う可能性があると思われるため、企業の新人研修で消費者教育を行うことで、消費者被害の防止を図ることができるだろう。このように、あらゆる場面を活用し、法律で明記されている消費者教育を身近なものにしていく必要がある。
(文責 消費者委員会委員 大森 節子)
参考資料
目次
参考資料1
学校における消費者教育に関するヒアリング調査
- 【調査の概要】
- ・調査対象:都内の大学の学生9名(3年生及び4年生)都内の大学院の学生2名(修士1年生及び2年生)
- ・調査時期:平成28 年5月25 日
- ・調査目的:調査対象の学生に対して、消費者教育に対するイメージや、大学入学時までに受けてきた消費者教育等について調査を行うことにより、学校における消費者教育の実態について把握する。
- ・調査項目:
- 1 消費者教育のイメージ
- 2 これまでに受けてきた消費者教育
- 3 消費者事故・トラブルに遭った場合の対処等
- 4 今後受けたい消費者教育等
- 5 消費者教育を行う時期・方法
- 6 消費生活センター
- 7 成年年齢引き下げ
- 【ヒアリングの回答】
- 1 消費者教育のイメージ
- ・「消費者教育」という言葉を聞いたことが無く、イメージがつかみづらい。
- ・「消費者教育」という言葉は知っているけど、具体的なイメージは無い。
- ・詐欺などの悪質商法に遭った際の対処についての教育というイメージ。
- ・(消費者教育の内容は)知らないといけないものだが、(実際は)知らないものというイメージ。
- 2 これまでに受けてきた消費者教育
- ア 現在通っている大学等における消費者教育
- ・入学時のオリエンテーションで配布された資料の中に消費者教育に関するもの(部屋の賃貸借契約、マルチ商法に関する注意点等)が含まれていたと思うが、内容はよく覚えていない。
- ・金融・保険について企業の人が外部講師として教えてくれた。臨場感のある講義で興味を持つことができた。
- ・オリエンテーションの際、マルチ商法等の注意喚起があったと思う。また、近隣の大学等で学生を狙った消費者トラブルがあると、大学から注意喚起のメールがくるようになっている。ただ、興味が無い人はメールを読まずに削除しているようだ。
- イ 小学校、中学校、高等学校における消費者教育
- ・高等学校の政治経済の科目で製造物責任法(平成6年法律第85 号)について習った。
- ・消費者教育に関する単語(クーリング・オフ等)は覚えたが、身についているか自信は無い。
- ・おそらく中学生の時と思うが、警察の人が学校に来て、スライドや寸劇で架空請求などを習ったが、危険ドラッグなど消費者教育と直接関係のないものも含まれていた。
- ・高校生の時に、携帯電話のゲームでの課金トラブル(親のクレジットカードを無断で利用して高額な課金になるもの)を外部の方に教えてもらった。また、悪質商法のDVD を見たが、内容はよく覚えていない。
- ・食品製造について、(消費者としてではなく)製造する側の責任について習ったと思うが、よく覚えていない。
- ・中学生の時、警察の人からプロフィールを書き込むサイトから個人情報が流出することや、クレジットカード会社の人に多重債務について教えてもらったがよく覚えていない。
- ・自分が高校生の頃、冷凍ギョーザに関する問題があった。社会的関心が高く、授業でも関係する法律などを教えてもらった。
- ・小学校、中学校の家庭科の授業で遺伝子組み換えについて習った。
- ウ 印象に残っている授業とその理由
- ・警察の人など、外部の人に教えてもらった場合、いつもと違う人に教えてもらうので、授業を受けたことは覚えている。ただ、イベントとして覚えている面が大きく、内容はあまり覚えていない。
- ・先生が自分の経験として消費者被害を教えてくれたので、印象に残っているが、内容はあまり覚えていない。
- ・小学校の時に田植えを体験した。食べ物の大切さが良く分かり、食品ロスをしないように気を付けている。田植えを実体験していることも良かったと思う。
- エ 受けたかった消費者教育の分野
- ・大学生になってクレジットカードを作ったが、カード会社がどんな審査を行っているかなど、仕組みを知っておけばよかったと思う。
- ・アルバイトで収入が103 万円を超えると親の扶養を外れてしまうが、根拠など詳しいことは分からないので知っておけばよかったと思う。
- ・スマートフォンが普及しており、架空請求などのトラブルがあるが、対処方法について小学校、中学校くらいからでも教えてくれたらと思った。
- ・大学に入学する際、部屋を借りたが知識が無かったため、親任せになってしまった。賃貸借についてもっと知っておけばよかった。
- ・大学生で、フェアトレードや児童労働について教えてもらった。高校生の時に安価な服などを買っていたが、安さの背景に児童労働などがあることを知っておけばよかったと思った。
- ・消費者トラブルで被害を受けたことは無いが、万が一被害に遭った場合の相談先が分かると良い。
- ・詐欺等の手法が分かる動画などがあると良い。
- ・金融商品等の金銭が関係するものは、理論だけ教える傾向があると思う。商品の仕組みや、大きく儲かることもあれば、大きく損することがあるなど実態についても教えるべき。
- 3 消費者事故・トラブルに遭った場合の対処等
- ア トラブルに遭った経験の有無と対処
- ・友人からマルチ商法と思われるパンフレットを渡された。パンフレットは破棄した。
- ・中学生の時、架空請求をされ、対処方法が分からず連絡をしてしまった。支払えないと説明したら請求されずにすんだ。
- ・親類がSNS のID を乗っ取られ、身内に電子マネーを買ってほしいというメッセージが送られてきたため購入して、電子マネーのID を教えてしまい、お金を詐取された。お金は取り戻せないと思い、諦めた(警察等には相談していない。)。
- ・親類が、プロバイダからプロバイダの変更を勧められ、プロバイダを変えたところ、料金が高くなったため、解約を申し出たところ断られた。クーリング・オフについて習った記憶があり、親とも相談し、プロバイダにクーリング・オフを申し込んだところ、解約できた。
- ・高校生の時に架空請求をされ、親に相談した。親が調べた結果、対応する必要が無いことが分かった。
- ・通販サイトで買ったものが、期日までに届かず、また、汚れていたので、これから返品を求めるか等検討している。
- ・親類の家に、オレオレ詐欺の電話があった。詐欺と気が付いたので、被害はなかったが、気が付かない場合もあり怖いと思った。
- ・スマートフォンを使っているときに、クリックと同時に画像が表示されスマートフォンが動かなくなった。いくつかソフトを削除することにより、画像は表示されなくなり、使用できるようになった。
- イ トラブルに遭わないために気を付けていること
- ・通信販売のサイトを利用するときは、会社の場所、連絡先、使われている言葉が不自然ではないかチェックして、あやしいと思ったところは使わないようにしている。
- ・通信販売サイトなどに、クレジットカードの番号を安易に入力しないようにしている。
- ・インターネットで買い物をする場合、バナー広告から誘導されるサイトは信用できないので、正規のサイトから買い物をするようにしている。
- ・買い物をする場合には、購入する店の評価(注文した商品を期日までに届けている等)や製品についてインターネットで調べるようにしている。
- 4 今後受けたい消費者教育等
- ア 今後受けたい消費者教育の分野
- ・税金について、学生の間は払わなくて良いことが多いと思うが、将来的には支払う必要があると思うので、知りたい。
- ・通信販売サイトを利用するが、規約の内容がよく分からないので知りたい。
- ・「トクホ」のマークなど、製品についているマークについて良く知らないものもあるが、生活に関係するものなので知りたいと思う。
- ・大学を卒業後、一人暮らしをする予定なので、家賃、光熱費等生活にかかる費用や、一人暮らしにありがちなトラブルについて知りたい。
- イ 受けやすい消費者教育の方法
- ・消費者トラブルの事例や解決方法がまとまったサイトがあれば、時間がある時に勉強できる。
- ・年齢に適した教材など、対象が明確になっている教材があれば勉強しやすい。
- ・現在大学で受講している講座のほか、(消費者教育に関する)集中講座があれば受けてみたい。
- 5 消費者教育を行う時期、方法
- ・消費者教育の内容は、小学校、中学校、高等学校で教えてもらってもなかなか覚えられないが、クーリング・オフ等の言葉を少しでも覚えていれば将来トラブルに遭った時に役に立つので、小学生くらいから継続的に教えるのが良いと思う。
- ・小学校、中学校、高等学校で消費者教育は少しの時間しか習わなかったと思う。散発的に習っても忘れてしまうので、週1時間でも授業で扱えば知識が積み重なって良いと思う。
- ・消費者教育は小学生など、低年齢の時期から教えることが大切。大学で消費者教育を行うことも大事だが、大学生は興味が無い科目は履修しない。
- 6 消費生活センター
- ・消費者被害に遭った時に消費生活センターに相談しようと思って検索したが、どこのセンターに電話すれば良いか分からず、結局相談しなかった。
- ・消費生活センターは知っているが、高額なトラブルなど被害が大きなものでないと相談してはいけないという印象をもっている。気軽な気持ちで相談できるものであれば利用したい。
- ・消費者トラブルに遭った際、電話で相談したい人とメールで相談したい人が居ると思うので、消費生活センターでは両方とも利用できるようにしてほしい。
- 7 成年年齢引き下げについて
- ・18 歳までに消費者教育をしっかりやってから引き下げないと被害が増えると思う。消費者教育をしっかりすることが必要ではないか。
- ・18 歳で大学に入学し、初めて一人暮らしを始めたり、クレジットカードを作る人も多いと思う。20 歳までの2年間でいろいろなことを知ることができるので、18 歳になってすぐに成人として責任を負うことになるのは大変と思う。
- ・18 歳で成人として扱われるのは大変と思うが、保護者から早く自立したい人にとっては、良いと思う。
- ・18 歳は、大学受験や高校を卒業するタイミングであり、大学入学、就職等、これまでと大きく環境が変わる時期。20 歳までの2年間はいろいろ経験できる大切な期間ではないか。
参考資料2
消費者教育コーディネーターについて~若年者の消費者教育の視点から~
岡山県消費者教育コーディネーター
矢吹香月
1.岡山県の取組みについて
(1) 岡山県消費者教育推進計画
平成24 年12 月、消費者教育を総合的・一体的に推進することを目的とした「消費者教育の推進に関する法律」が施行され、平成25 年6 月「消費者教育の推進に関する基本的な方針」(以下、「基本方針」という。)が閣議決定されたことを受け、岡山県では、平成26 年3 月基本方針に沿って、自ら考え自立した消費者を育成するために「岡山県消費者教育推進計画」(平成26 年度から30 年度)を策定した。なお、計画の策定に当たっては、県民の意識調査を実施するとともに、岡山県消費生活センター(以下、「県センター」という。)の相談実績を分析し、岡山県消費生活懇談会(岡山県消費者教育推進地域協議会)の意見や県民のニーズを踏まえた。
この計画は、消費者教育の推進について、3 つの基本目標と13 の重点目標を定めた。
また、期間中の重点施策としてマル1高齢者・障害のある人を中心とした消費者教育の推進、マル2学校教育における消費者教育の推進を掲げ、県センターを消費者教育の拠点として位置付け、消費者教育を推進するコーディネーターを配置することとした。
(2) 消費者教育連携の仕組み
マル1平成18 年6 月岡山県における消費者教育に関する行政機関等の連絡調整及び協議を行うため、岡山県消費者教育連絡協議会を設置し、毎年担当者会議を開催し、連携を図り教育計画や基本計画の進捗状況等調査を行っている。
マル2教育委員会の人材応援バンクに、学校へ出前事業ができる機関として登録し、登録団体と学校が出会う「おかやま教育支援活動メニュ―フェアー」に平成26 年度より参加し、学校教育現場の教員に直接出前授業の概要を紹介している。昨年度は、メニューフェアーに参加されていた中学校の教頭先生に中学生の消費者問題の現状について説明したところ、後日、講師派遣依頼があった。
マル3平成26 年度から教育委員会とくらし安全・安心課が連携して、ネットトラブル防止教材のタブレットパックを作成し、貸出する事業を行っている。小中教員に使用方法を含めた貸し出しについての説明会が開催された時に出向き、最新の消費者トラブルについて講座を実施した。
マル4平成27 年度より消費者庁の先駆的プログラム事業として3 年計画で体系的な教材開発をしている。この事業の特色は、「教材検討委員会」を設置し大学教授、高校教員、幼稚園園長、金融広報委員会、県教育委員会、岡山市教育委員会をメンバーとして構成している点があげられる。平成27 年度は「契約」の基本を法教育としての消費者教育の視点を取り入れた発達段階に応じた教材を作成した。
- ア)幼児期は「ももたのおかいもの」と題する紙芝居で、"自由"に主眼をおいた<きまり><やくそく>の意味について学ぶ教材である。
- イ)小学生期では多発している消費者問題であるオンラインゲームを題材とし、小学生になったももたが父親のクレジットカードナンバーをこっそり入力して50 万円のアイテムを購入する教材である。<きまり><やくそく>を守ることの意義、守れないときには話し合いをして新たなルールを作ることの大切さを学ぶ教材である。
- ウ)中・高校生期では、高校生になったももたが私的自治の原則、契約の基本を学び、未成年者契約の取り消しはなぜできるのかを深く学び、消費者と事業者間の格差やクーリング・オフ制度について考える授業につながる教材である。
これらの教材は、検討委員会で検討しモデル授業において教材を実際に使用して児童や生徒の反応を確認しながら作成した。
また、学校現場の教員が負担なく使用できるように、指導解説書とワークシートやパワーポイントを用いた映像等のCDを一つのパックとするように工夫した。平成28 年度はこれらの教材を学校や各機関で使用してもらい、不都合な点等意見を集約してさらにブラッシュアップしていく予定である。
また、今年度も新たな教材作りに取り掛かっている。
マル5市町村との連携については、各市町村の状況に応じてどのような支援をしながら連携することができるかを考えなくてはならない。特に、学校現場に出向く講座については、消費生活センターが設置されていて数名の消費生活相談員が配置されている市の場合は、県センターが作成した教材の提供や県が主催する事業・講座の声掛けなどをして、参考にしていただくようにしている。消費生活センターが設置されていない市町村の場合は、県センターが中心となって講座を実施している。
- -例-
- ア)平成25 年度は県立高校での消費者問題の授業を実施する際、岡山市の担当者の方にお声掛けをして、授業で見ていただいた。その後、市内の県立高校からの依頼があった場合、自信を持って講座をしていただくように支援した。
- イ)平成26 年度は津山市内の小学校で授業をする際、津山市の担当者の方にお声掛けをして、授業を見ていただいた。
- ウ)同じく平成26 年度は岡山県高等学校家庭科教育協会で講座をする際、岡山市にお声掛けをして講座にお越しいただき、市内高校の家庭科教員と連携ができるように体制創りをした。
- エ)平成27 年度は前出の幼児期用教材「ももたのおかいもの」のモデル授業を実施する際は、岡山市消費生活センターと連携して一緒に実施した。
- オ)平成28 年度は、中学生用教材作成のモデル授業を早島町の消費生活相談窓口と連携して町立中学校で実施する予定である。
- マル6 他機関との連携・協働については、様々な機会で教材の作成と連携体制の構築をしてきた。
- ア)若年者層に対する消費者教育教材作成に関しては、平成24 年度は中国学園短期大学の学生と連携して「若者による若者のための消費者トラブル対処法」のパンフレットを作成した。大学生はパンフレットつくりに参加し他者に伝えることを通して自ら消費者問題とは何かを学ぶことができたようだ。こうした経験は、大学生の消費者教育にも有益なことであると考え、前出の消費者教育教材開発事業では、中・高生の教材作成やモデル授業に大学生も関与してもらうようにした。また、前出の消費者教育教材開発事業においては、教材作成について金融広報委員会に検討委員会のメンバーに入っていただき連携している。
- イ)連携体制構築については、平成26 年度より総務省eネットキャラバンと連携して、消費生活相談員が仕事として講座を担当することができ、最新の生情報を伝えることができるようにした。
- ウ)高齢者に対する教材の作成に関して、平成25 年度は美作大学の学生と連携して「元気に笑顔で暮らす~虎の巻~」のパンフレットを作成した。大学生は教員を目指すものや高齢者施設への就職を希望するものなど有志であったが、高齢者被害の現状を学び、社会の一員としてどのように社会とかかわっていくことが重要かを深く学ぶことができたようだ。その後、有志の学生を中心とした「みまだいコンシュマーズ」が組織され、岡山県消費生活センターのボランティア講師として登録してもらい、寸劇などを交えた啓発講座を担当してもらっている。
- エ)高齢者に対する消費者教育の連携体制構築については、財務局、消防組合との連携を構築した。また、民事調停協会との連携を構築した。
マル7平成27 年度県センターが若年者層を対象に実施した消費者教育の実績は、下記表のとおりである。
| 幼稚園・保育園 | 小学校 | 中学校 | 高等学校 | 大学 | 支援学校 | 専門学校 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1回 | 2回 | 2回 | 6回 | 8回 | 2回 | 1回 | 22回 |
2.コーディネーターの資質について
(1) コーディネートとは
コーディネートの意味を現代用語の基礎知識(2015)で調べてみると「調整する、統合させる。組合せ衣料品(家具)。」と記述されている。そこで、消費者教育をコーディネートすることの意味を当てはめると、マル1消費者教育をする人と消費者教育をする人、マル2消費者教育をする人と消費者教育を受ける人、マル3消費者教育をする人と消費者教育に必要な情報、マル4消費者教育を受ける人と消費者教育に必要な情報、マル5消費者教育をする人と消費者教育に関する資源、マル6消費者教育を受ける人と消費者教育に関する資源を、ニーズや条件を考慮して適切に結びつくように「調整」することとなる。
(2) 消費者教育コーディネーターとは(注37)
コーディネーターとは、コーディネートする人のことを意味することから、消費者教育コーディネーターとは、消費者教育をコーディネートする人のことである。
そこで、消費者教育コーディネーターの役割について、考察すると2 つの役割を示すことができる。
マル1人と人、人と情報、人と資源を当事者のニーズに合うように調整する役割がある。
- 具体的には、
- ・消費者問題・消費者教育についての情報収集・発信する役割
- ・当事者相互の要望を調整する仲介的役割
- ・消費者教育資源を上手く利用できるように世話をする役割
- ・消費者教育に関する経験等を通してより良い方向に向かうように牽引する役割などを挙げることができる。
マル2人と人、人と情報、人と資源を結びつけて、新たな消費者教育の場を創出するなど企画・提案する役割がある。
- 具体的には、
- ・新たな消費者教育の場の創設をする役割
- ・異なる団体の当事者を結びつけて、新たな消費者教育の創出をする役割
- ・有意義な事業をするために、新たな協力機関等を見出す役割
(3) 消費者教育コーディネーターの資質・能力
消費者教育コーディネーターに期待される資質については、消費者教育推進会議地域連携推進小委員会において以下の3 つの資質が提示されている。
マル1消費者教育を広めるため<魅力的な講座等の企画・立案・説得>する資質
マル2消費者教育の実施を働きかけるため<調整を行う、共感を生む>資質
マル3消費者教育の関係者をつなぐため<調整を行う、共感を生む>資質ここでは、「広める」「働きかける」「つなぐ」3 つの消費者教育コーディネーターの役割と「広める」ための資質として<企画・立案・説得>、「働きかける」ための資質として<調整・共感>、「つなぐ」ための資質として<調整・共感>が示されている。これら提示された資質を実践に即してより具体的に整理するとマル1専門性マル2人間性マル3ネットワークという3 つの要素と「信頼・共感」というキーワードを導き出すことができる。
- マル1 専門性・・・・・・・・・知識・技能
- ・消費者問題の歴史・消費者問題の現状・消費者問題の法的観点
- ・学校教育の現状・教材化に向けての知識
- マル2人間性・・・・・・・・・情意・態度
- ・信頼性に結びつく人間性・他者と協働して社会参画
- マル3ネットワーク・・・・・・思考力・判断力・表現力
- ・個人が持っているネットワーク
- ・行政が持っているネットワーク
講座・研修会・研究会等への参加、交流会での意見交換、発表の場
考察する力(多角的に)
構想する力(複数の立場や意見を踏まえ、課題を把握、構想)
説明する力(自分の考えを論理的・効果的に説明)
これら3 つの要素が重なりあい、さらにマル4ニーズの発見マル5コミュニケーションマル6企画・提案という資質が求められ、もっとも重要となる「信頼される」「共感する」という資質を導き出すことができると考えられる。これらの関係を図で示すならば以下の通りである。
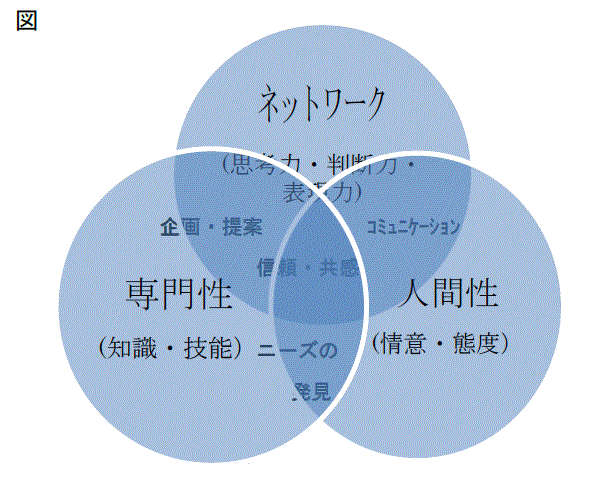
(4) 消費者教育コーディネーター養成の方策
消費者教育コーディネーターを養成するための研修として、どのような視点でプログラムを企画する必要があるかについて模索中ではあるが、岡山県では平成27 年度に消費者庁の先駆的プログラムとしてコーディネート人材養成講座を開催した。この講座は、全16 回に亘る講座で、消費者教育コーディネーターの資質を養うものであったと思われる。この事業を終え、再度検証し不足していた資質の領域も明確になった。
国立教育政策研修所社会教育実践研究センターの調査研究報告書(注38)を参考に、消費者教育コーディネーターを養成するプログラムを考察するならば、以下のとおりとなる。
消費者教育コーディネーター養成研修プログラム例
| 資質・能力の領域 | 学習テーマ | 主な学習内容 |
|---|---|---|
| 1.専門性 | 消費者問題の基礎 | 消費者問題の現状と関連する法律等 |
| 学校教育の基礎 | 学校教育・学習指導要領等教育の基礎、教材作成の注意点、学習指導案の作成 | |
| 地域組織・活動領域の基礎 | 地域の教育支援方策、地域の教材等の収集・活用方策 | |
| 個人情報保護 | 個人情報保護、人権等 | |
| 2.ネットワーク | ネットワークの理解 | ネットワーク形成方法、連携・協働の意義 |
| ネットワーク診断 | 人脈リスト作成等 | |
| 情報収集方法 | 消費者教育についてどこからどのような情報をえることができるか情報源の確認 | |
| 3.人間性 | コミュニケーション・スキル | 話し方、共感すること、提案のしかた、説得等 |
| カウンセリング・スキル | 傾聴についてロールプレイング | |
| 4.企画・提案 | 企画・提案 | 講座作成方法、プレゼンテーション方法など実演、PDCAについて |
| 5.コーディネート | コーディネーターの役割 | 役割と活動例 |
- (注37) コーディネーターの役割については、文部科学省国立教育政策研修所社会教育実践研究センターが調査した報告書を参考にした。国立教育政策研修所社会教育実践研究センター『平成19 年度社会教育を推進するコーディネーターの役割及び資質向上に関する調査報告書』(2008 年4 月)、国立教育政策研修所社会教育実践研究センター『平成20 年度社会教育を推進するコーディネーターの役割及び資質向上に関する調査報告書』(2009 年3 月)。
- (注38) 国立教育政策研修所社会教育実践研究センター『平成20 年度社会教育を推進するコーディネーターの役割及び資質向上に関する調査報告書』(2009 年3 月)。
3.コーディネーターが活躍できる環境
(1) 自治体の役割
コーディネーターを配置するときには、自治体はコーディネーターが何をするかを明確に示す必要がある。消費者教育推進計画に基づいて配置されると思われるが、どのような役割を担ってもらうかが重要である。例えば、マル1教育委員会と消費者行政との壁を取り除くため、マル2消費者教育を学校教育現場に取り入れてもうらため、マル3消費者教育教材を作成するため、マル4消費者教育を学校の授業でしてもらうため等の目的で教員OB・OGを消費者教育コーディネーターに就任していただくという場合がある。この場合は、教員OB・OGは消費者問題について専門家ではないので、消費者問題や行政内部組織との連携について行政のフォローが重要である。
また、消費生活相談員を消費者教育コーディネーターとして配置する場合がある。例えば、マル1消費者教育を学校の授業でしてもらうため、マル2消費者教育教材を作成するため、マル3消費者教育の場を開拓してもらうため等の目的がある。この場合は、消費生活相談員は教えるプロではないので、教える技術等が未熟で学習指導要領について詳しくないので学校や教育委員会との橋渡しを行政がフォローすることが重要である。
しかし、目的は消費者市民社会に参画する消費者市民を育成する教育を行うことであり、この目的を達成する手段として消費者教育コーディネーターが存在していることを忘れてはいけないと考える。手段が目的化することで消費者教育は「絵に描いた餅」となってしまう恐れがある。目的を明確にして、目的達成の手段として消費者教育コーディネーターに何を求めるかを行政は明示する必要がある。
(2) 教育委員会との関係
教育委員会と消費者行政の壁を消費者教育コーディネーターに求める場合がある。学校現場は○○教育が次から次へと降ってくるため忙しく、消費者教育だけに時間をさいてくれることはないことを共感する必要がある。学校現場が何を求めているかを把握し、教育委員会にはお願いしたいことを具体的に示すことで高い壁は低くなるのではないだろうか。きめ細かいオーダーメードを消費者教育コーディネーターと行政職員とでやり取りする必要がある。
(3) 環境整備
消費者教育コーディネーターを配置して終わりとするのではなく、共に歩く行政職員の存在が重要である。消費者教育は消費者教育コーディネーター一人がするものではなく、様々な人々と連携・協働するからこそできるものであることを行政側も認識し、消費者教育コーディネーターを信頼して共に歩むことが息の長い消費者教育に繋がっていくと考える。消費者教育コーディネーターと行政職員が信頼して働ける環境を整備することが必要である。
4.消費者教育のあるべき姿について
(1) 消費者教育の基本姿勢
私の消費者教育に関する基本姿勢は、消費者教育コーディネーターを拝命する以前から「法教育としての消費者教育」である。「法教育としての消費者教育」とは、消費者として日常生活で起こる様々な契約を通して、法の背後にある<自由・責任・公正・正義>という価値を主体的に考えることができるように支援する教育である。
自由で公正な社会において求められる消費者市民とは、様々な考え方や価値観を持ち、多様な生き方を求める人々が、お互いの存在を承認し、尊重しながらともに協力して生きていくことのできる社会の形成に参画する消費者であると考えている。つまり、資本主義経済の市場においては、一人一人が自分にとって何が必要か、自分はどのようなライフスタイルを選択するかについて、まずは情報収集し、適切な情報の下で自らが取捨選択し、判断していくことで「生きる力」が育成されると考える。但し重要なことは、自ら判断する際にどのような価値を重視するか考える必要があるがそのときに、自分の利益のみではなく公的利益も考慮するような基準があることに気づくような教育内容にすることである。自律した消費者を育成する消費者教育は、消費者問題を教材として自分を大切にしつつ、自分以外の周りの人々との協力関係を適切に構築していく能力を身につける教育で、自分の考えと異なる意見にどのように向き合い、合意を形成することができるかを考える力が、消費者市民社会の中で生きる力になると考えている。
(2) 消費者教育コーディネーターになった経緯
消費者教育コーディネーターを拝命する以前から、こうした消費者教育に関する基本姿勢であった。県センターの消費生活相談員は非常勤職員で、勤務日以外は、中高一貫校(私学)の社会科教員、大学の非常勤講師として教壇に立っている(現在は大学のみ)。学校現場はもとより、県センターでの消費者教育講座・啓発活動においても、同姿勢で活動していた。平成22 年度は、「知っておきたい契約・取引の基礎知識(注39)」と題する消費者教育副読本を作成し、翌23 年度には、その消費者教育副読本の「教員向け解説書」を作成した。平成24 年度は、「消費生活学」の非常勤講師をしていた短期大学において、学生が学んだ消費者問題を、県センターが作成するパンフレットに関与して伝えるという手法で講義を行い、「若者による 若者のための 消費者トラブル対処法」を作成した。平成25 年度は、県センターが高齢者向けのパンフレットを刷新するとのことであったので、県北部にある大学と連携して作成することを提案し、大学教員と連携して、大学生にマル1消費者問題の基本知識マル2高齢者の消費者被害について講座を行い、「高齢者のための 元気に笑顔で暮らす~虎の巻~」のパンフレットを作成した。
- (注39) 平成 22 年度消費者教育教材資料表彰優秀賞受賞((公財)消費者教育支援センター主催)こうした姿勢が消費者教育コーディネーターを拝命する契機となったと考える。
(3) 消費者教育の内容
消費者教育の内容は、発達段階に応じた内容のものが必要となる。さらに、トラブルや被害に遭いやすい内容のものを取り入れ、社会情勢の変化にも機敏に対応することが重要である。消費者教育の栄養は“消費者の声”である。消費生活センターが消費者教育拠点となることは、消費者の生の声を直接聞いている消費生活相談員が関与しているということに意義がある。相談者の声から社会問題を抽出し、教材とすることが現代社会で「生きる力」を育むことにつながっていくのではないかと考える。学校教員は教えることのプロであるが、教える内容である消費者問題のプロではない。そこで、消費生活センターとうまく連携をして実践に基づいた教育内容を考えることが大切ではないかと考える。
消費生活センターは、消費者の声を教育現場に伝え、消費者問題に対する教員の認識を高めてもらうとともに、両者が一体となって将来を担う世代を育成しなくてはならない。また、自由で公正な社会の形成に主体的に参画できる「自律的な消費者」として育成する取り組みを進めるためには、文部科学省との息の長い連携が必要となる。
- ―例―
- ・今年度の高校卒の新入社員対象の消費者教育講座(造船会社で多数が男性)では、若者用のパンフレットを用いながら、講座担当の消費生活相談員が受けている 若い男性特有の消費者問題の一つである包茎手術の事例を紹介した。若い男性だからこそ陥りやすい消費者被害事例を伝え、契約する際には慎重に考慮しないといけないことがあること、困ったときには恥ずかしがらずに相談すること等を伝えた。消費者教育コーディネーターは、このように講座担当の消費生活相談員に消費者教育の内容について相談を受け、助言等を行っている。
- ・小学生期では、オンラインゲームに関するトラブルが多発している現状を踏まえ、教材を作成した。また、このオンラインゲームに関する教材の授業は、授業参観日に実施させていただいた。オンラインゲーム関係については、家庭教育との関係もある内容であることから、授業参観日に実施することは有益な方法であった。
5.消費者教育を推進するために国として取り組むべきこと
(1) 「点」⇒「線」、「線」⇒「面」への実効性の高い連携のシステムの構築消費者教育を社会に根付かせ、消費者市民社会を構築するためには、消費生活センターの充実が必要である。消費者の生の声を自由で公正な社会の形成につなげていくためには、多くの機関との連携が重要と考える。
岡山県の取り組みの中で、実施可能と思われる取組みは国全体の取り組みにつながることが望ましいと考える。このような環境の整備を担うのが国の大きな役割ではないだろうか。
(2) 県と市町村の役割分担の明確化と地方の相談体制の充実に向けた継続的支援
市町村は、住民に身近な相談窓口として、「寄り添う」「掘り起こす」「センサー機能を地域に細かく張り巡らせる」という役割が期待され、また、きめ細かな情報伝達力、ワンストップでの機動的かつ総合的な対応力など、都道府県にはない優れた特性を備えている。
一方で、都道府県は、地域からの複雑化・高度化する相談に応じるという課題と基礎自治体を的確にバックアップするという重要な役割を担うことが期待されている。
しかしながら、こうした県と市町村の役割分担ができている自治体はまだ数少ないのではないだろうか。
消費者安全法が施行され、消費生活センターの法的位置づけが明確にされ、役割分担について移行段階にある現在、超高齢社会における基礎自治体の相談窓口の重要性の高まりを踏まえた今後の消費生活センター体制のあるべき姿に関する国の一定の方向付けが必要と考える。
また、地方消費者行政活性化基金により充実・強化が図られた地方の消費生活相談体制を後退させることがないよう、消費者の生の声が消費者教育の栄養素であることを踏まえると、特に基金を契機に新設された消費生活センター及び今後新たに消費生活センターの設置を目指す基礎自治体への支援を継続することが重要ではないかと考える。

