委員プロフィール
- 最新情報
青木秀子(前花王株式会社常勤監査役)

略歴
昭和53年京都大学薬学部卒業。製薬会社勤務を経て、昭和57年花王石鹸株式会社(現 花王株式会社)入社、花王生活科学研究所配属。平成14年品質保証本部品質保証センター長、平成19年から平成30年まで品質保証本部長。平成20年理事に就任、平成22年執行役員、平成26年から平成30年まで株式会社カネボウ化粧品取締役を兼務、平成27年常務執行役員、平成31年常勤監査役、令和5年退任。消費者教育推進会議委員、国民生活センター特別顧問・紛争解決委員会委員等を歴任。
メッセージ
今般の新型コロナ感染症拡大が世界的かつ長期化する中で、あらためて日々の暮らしの安全・安心を守ることの重要性を痛感するとともに、デジタル社会の急速な進展、地球環境問題への危機感、SDG’sへの取組みの加速など、消費者を取り巻く大きな変化が押し寄せています。
消費者の意識・行動もますます多様化する中で、高齢化の進展、成年年齢引き下げ、デジタル化、コロナ禍による経済基盤の脆弱化や孤立化する消費者の増加等が加わり、新たな消費者保護施策や啓発・教育の必要性が高まっています。
一方、国際社会の共通認識となっているサステイナブルな社会を構築するためにさまざまな取組みが進んでいますが、消費者や産官学がいかに連携・協働して大きな取組みにしていくかが重要であり、消費者政策も保護から「つかう責任」、そして協働へ、より全体最適な舵取りが必要です。
この持続可能な経済社会形成への協働という視点を常に意識しながら、これまでの事業者としての取組みや、消費者政策のさまざまな委員としての経験を活かして、消費者委員会でさまざまな課題を検討していきたいと思います。
飯島淳子(東北大学大学院法学研究科教授)

略歴
平成7年東京大学法学部卒業。平成14年東京大学大学院法学政治学研究科博士課程単位取得退学(平成15年9月 博士(法学))。平成15年東北大学大学院法学研究科助教授。平成19年同科准教授。平成24年より現職。令和2年より同大公共政策大学院長を兼務。専門は行政法、地方自治法。地方制度調査会委員、民間資金等活用事業推進委員会委員、社会資本整備審議会委員等を歴任。主著に『行政法』、『事例から行政法を考える』(いずれも共著)、『市民のための行政法、公務員にとっての行政法』等。
メッセージ
感染症のまん延や自然災害、高齢化・人口減少や地域・地球の持続可能性の危機はそれぞれに、一人ひとりの消費者としての側面にも大きな影響をもたらしています。そして、消費者問題に対応するための消費者行政も多岐にわたる課題に直面しています。深刻化するばかりの資源制約のなかで連携が必要とされ、急激なデジタル化に対して個人情報の保護と利活用のバランスが問題となり、消費者像―社会像の捉え方自体が問い直されています。
消費者法は、民事法と行政法の“協働”が必須となる最先端の法分野でもありますが、行政法の研究・教育に携わる立場から、行政法の古典的な図式に収まりきらない現実を直視し、「一人」を救うための実践に敬意を表しつつ、しかし一つひとつ異なる個別の現実に対応するための一般的な制度・政策の意味を考えていきたいと存じます。消費者委員会に心血を注いでいた元同僚と同じく、情熱と使命感をもって毎週の会議に臨んでいる委員から刺激と示唆を受け、2年間微力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
生駒芳子(ファッション・ジャーナリスト、一般社団法人日本エシカル推進協議会会長)
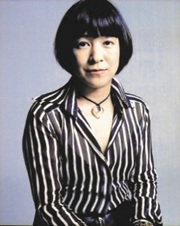
略歴
昭和52年東京外国語大学フランス語学科卒業。同年、編集プロダクションぐるーぷぱあめ入社。平成10年VOGUE NIPPON 副編集長、平成14年にはアシェット婦人画報社に入社し、ELLE JAPON 副編集長やmarie claire Japon 編集長等を務める。現在、株式会社アートダイナミクス代表取締役社長、有限会社UNDER GROUND代表取締役社長、伝統工芸ブランド『HIRUME』総合プロデューサー、日本エシカル推進協議会会長等を務める。消費者委員会委員等を歴任。
メッセージ
この度第6次に引き続き、第7次消費者委員会で委員を拝命いたしました。長らくファッション界において、トレーサビリティ、サステナビリティを取材・研究・伝達する「エシカル」を推進する仕事に力を注いで参りました。2017年からは、日本エシカル推進協議会の副会長(2022年6月より会長)として、エシカルを推進する数々のプロジェクトに参画。2021年10月には「JEIエシカル基準」を発表いたしました。中小企業や地域企業、行政の皆様が、自らの組織のあり方や活動について、環境や人権の視点から判断する「エシカル」の基準をご紹介しています。また、昨年からは、日本においてサステナブル・ファッションを普及させる活動も推進しています。消費者に必要な情報、正しい情報を届けることは、消費者の自立を促し、結果として被害を防ぐことにつながります。またエシカル消費の推進は、優良な活動をする企業を育て、応援することにもなります。Shopping for better life--エシカルな消費が社会の未来を作るという意識を育てる道筋を、この委員会で考えていければと思っております。
受田浩之(高知大学理事、副学長)

略歴
昭和59年九州大学大学院農学研究科修士課程修了。昭和61年九州大学農学部助手。平成3年高知大学農学部助教授、平成16年同教授、平成17年より同地域連携推進本部長及び国際・地域連携推進センター長を兼務、平成18年より同副学長(地域連携担当)を兼務、平成27年より同地域協働学部教授に就任し、地域連携推進センター長(名称変更)を兼務。平成31年より現職。専門は食品分析学、食品化学、食品機能学。消費者委員会委員、消費者委員会臨時委員等を歴任。
メッセージ
第5次、第6次から引き続き第7次消費者委員会委員を拝命致しました。第6次は任期前半でコロナ禍に突入し、消費者を取り巻く様々な問題が発生致しました。消費者委員会も対面開催が困難になり、オンライン開催を余儀なくされました。今期もオンラインでのスタートになりますが、これまでの4年間にわたる委員経験に基づき、10人の委員の力を最大に発揮できる環境づくりに貢献してまいりたいと考えています。
一方で、自らの食品科学における研究者としての経験を基に、食品関係の部会において、消費者の皆様の声をしっかりと受け止めた議論を展開してまいります。特に第5次食品表示部会で提言した「食品表示の全体像に関する報告書」の実現に向けて、デジタル化を視野に入れた食品表示の在り方について検討を進めてまいります。コロナ禍において電子商取引(EC)市場が拡大していることから、早急な整備を求める声に応えていく所存です。
この2年間どうぞよろしくお願い申し上げます。
大石美奈子(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 前代表理事・前副会長)

略歴
昭和54年奈良女子大学家政学部卒業。同年より高校家庭科教諭を務める。平成7年消費生活アドバイザー資格取得、社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント協会に加入。家庭科非常勤講師を務める傍ら牛乳乳製品や無洗米の消費者相談室にも勤務。平成24年公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会理事、平成28年より代表理事・副会長(令和4年まで)。消費者委員会委員、調達価格算定委員、中央環境審議会臨時委員、産業構造審議会臨時委員等を歴任。
メッセージ
コロナウイルスの感染拡大によりWeb会議など社会のデジタル化が進み、対面で話すことの重要性を再認識させられた2年間でした。再任にあたり、消費者委員会へのさまざまな御意見と真摯に向き合い、「コミュニケーション」をキーワードに、今期の委員の皆さまと共に課題解決に取り組んでいきたいと考えています。
喫緊の課題として、成年年齢の引き下げによる若者の消費者被害の未然防止にむけ、計画的、継続的に消費者教育を進めていくことが挙げられます。また、デジタル化の便益を高齢者も含め誰もが享受できるような消費者政策の実現が必須となっています。
世界的には、地球温暖化の影響による災害が多発しています。2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、次世代、また弱い立場の人々へ負荷を先送りにしないためにも、今こそわたしたちの意識や行動を大きく変えていかなければ取り返しがつかなくなってしまいます。同時に、2030年のSDGsの実現に向けて、消費者自らが、事業者との協働により取組みを進めていけるよう、消費者基本計画の工程表に省庁の壁を越え具体策を取り入れていきたいと考えております。
木村たま代(主婦連合会事務局長)

略歴
昭和60年お茶の水女子大学家政学部卒業。同年、松下冷機株式会社(現パナソニック株式会社)入社。昭和63年財団法人製品輸入促進協会等での勤務を経て、平成14年から主婦連合会会員。平成22年主婦連合会事務局に消費者相談員として勤務。平成28年主婦連合会消者相談室室長。令和元年より現職。経済産業省消費経済審議会臨時委員、消費者委員会委員、第25次東京都消費生活対策審議会委員等を務めた。
メッセージ
昨年から続く新型コロナ感染症が私たちに生活に与えた影響は大変大きく、さらにデジタル化が進むこれからの生活においては、誰もがぜい弱な消費者になってしまう可能性があることを痛感しています。消費者の日々の生活の中での疑問や不満などをどのように解決していくのか、未来を託す若い方に関心を持っていただくことについてなど、これまでの課題に加え、複雑化する情報化社会での新たな問題が加わり、課題が山積しています。誰一人取り残さない持続可能な消費者市民社会の実現のためには、消費者、消費者団体、NPO、行政、事業者などの各ステークホルダーが連携しながら、消費者の権利が尊重され、意見が反映されることが必要です。第6次の消費者委員会委員としての経験を活かし、消費者が安全・安心に暮らすことができるよう引き続き取り組んでまいります。どうぞよろしくお願いいたします。
黒木和彰(弁護士)

略歴
昭和60年九州大学法学部卒業。平成元年弁護士登録(福岡県弁護士会所属)。平成6年九州大学大学院修士課程修了。日本弁護士連合会では、消費者問題対策委員会委員長、COVID-19対策本部幹事等を歴任。
メッセージ
第7次の消費者委員会の委員を拝命いたしました。私は、2018年6月から2020年5月まで、日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の委員長として、また、適格消費者団体である消費者支援機構福岡の副理事長として、実務家の視点で消費者問題に取組んできました。
今回、第7次の消費者委員会の委員となりましたので、日弁連消費者問題対策委員会の約180名の委員と幹事の知見を得て、現在取組むべき課題と、中長期的に取組むべき課題について、積極的に意見を述べていきたいと考えています。
特に、2040年問題に代表される超高齢化社会において必要とされる消費者保護のための法制度や社会の在り方の問題、急激に進むデジタル化による社会の変化の中で、安心・安全な消費生活をどのように行うべきかという問題について、大変強い関心があります。20年後の社会変化を見据えて消費者委員会の委員として活動していく所存です。
後藤巻則(早稲田大学名誉教授)

略歴
昭和51年早稲田大学法学部卒業。昭和60年同大大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学。平成5年獨協大学法学部助教授、平成8年同大法学部教授、平成15年早稲田大学法学部教授を経て、平成16年同大大学院法務研究科教授。令和5年4月より現職。主著に『条解消費者三法』、『消費者契約と民法改正』等。
メッセージ
消費者問題は、その時々の社会経済情勢を背景にして、次々とその裾野を広げてきました。こうした中で、消費者行政には、新たに発生する多岐にわたる消費者問題に対し、迅速なだけでなく、変化に応じた柔軟な対応が求められます。
他方で、社会経済情勢の変化にかかわらず、不変の「消費者」像を見出すことができます。それは、消費者が、日々の生活を営む「生身の人間」であるということです。「十分な判断力をもたないで契約することがある」、「心(精神)が傷つきやすい」、「時として情動的になる」、といったことは、消費者が「生身の人間」だからです。これらの点は、経験的に理解されてきたことでもありますが、今日ではより理論的に究明され、立法などの場面で生かされつつあります。最近よく言われるようになった「脆弱な消費者」も、「生身の人間」につながる考え方です。
第7次の消費者委員会の委員長を拝命し、重責を担うことになりましたが、「生身の人間」の脆弱性を基本に、迅速かつ柔軟な対応を目指して、全く新しいスタートというつもりで取り組もうと考えています。
清水かほる(公益社団法人全国消費生活相談員協会中部支部長)

略歴
平成15年産業能率大学経営情報学部卒業。昭和58年中部電力株式会社入社。平成13年名古屋市消費生活センターにおいて、啓発業務等に携わり、平成15年より同センター消費生活相談員。平成25年より現職。消費者委員会委員、消費者教育推進会議委員、名古屋市消費生活審議会委員、愛知県消費生活審議会委員を歴任。
メッセージ
第6次に引き続き第7次の消費者委員会委員を拝命いたしました。
本協会は、全国の自治体等の消費生活センターで、相談業務などを担っている消費生活相談員を主な構成員とする団体です。消費生活センターは、安全・安心な暮らしを守る駆け込み寺です。消費生活相談は社会のセンサー、答えは現場にあります。契約書面等の電子化への懸念、新たな決済サービスによる消費者被害の増加、消費生活センターのデジタル化の遅れ、地方消費者行政の充実・強化の緊急性、消費生活相談員の待遇改善、消費生活相談員の担い手の育成等課題山積です。今後も国民が全国どこに住んでいても質の高い相談・救済を受けられ、安全・安心が確保される地域体制を築くために、地方の声を伝えます。特に民法改正による成年年齢引き下げにより、社会生活上の経験が乏しい若者が被害に遭わない体制づくりを実現したいです。
星野崇宏(慶應義塾大学経済学部教授)

略歴
平成16年東京大学大学院総合文化研究科博士課程修了。名古屋大学大学院経済学研究科准教授、東京大学大学院教育学研究科准教授を経て、平成27年より現職。行動経済学会副会長、国立研究開発法人理化学研究所AIPセンターチームリーダー等を務める。主著に『調査観察データの統計科学―因果推論・選択バイアス・データ融合』、『マーケティング・リサーチ入門』(共著)等。
メッセージ
消費者委員会は発足からまだ12年ほどの間に消費者保護に関わる非常に多くの課題について建議や提言を行い、各省庁の制度施策変更や法改正に寄与するところが大きかったと思います。これまでの素晴らしい活動実績は委員や事務局、関係各位の個人的な努力によるところが大きかったと思いますが、消費活動は時代とともに形を変え、その問題もまた変わりながら常に発生し続けるものです。いかなる時でも属人的ではなく組織的、継続的に消費者保護を行う仕組みを作ることが重要であり、政府全体で目指されているいわゆるエビデンスに基づく政策意思決定(EBPM) を消費者行政に根付かせるために、現場で日々得られるエビデンスを迅速に消費者保護に活かす仕組みづくりを私の専門的見地から提案できればと思っております。
また、我々「必ずしも合理的ではないヒト」の認知や行動のバイアスに関する行動経済学の知見が近年海外で消費者保護政策に実際に活用されています。我が国においても、これらの事例に学びながら我が国の社会や取引の形態を踏まえた行動経済学の活用を提案できればと思います。

